地上に存在するあらゆる分野にまたがり、表社会・裏社会を問わず優秀な人材を送り込む、それがA.G.E.と呼ばれる機関だ。
私はA.G.E.に所属し、コードネーム「蘭花」で呼ばれる特殊工作員。
潜入工作のプロフェッショナルとして育成訓練を受けた私は、まだ正規の任務について間もない若手だ。
その若手である私にその研究所への極秘潜入調査依頼が舞い込んできたのは、名をあげるまたとないチャンスだった。
ターゲットは、通称「ブラックドーム」と呼ばれる黒塗りの、ドーム状の建物。影で狂科学者と呼ばれる悪名高い科学者、カレン・ウィンターマンのラボラトリだ。
最近、アルカディア所属の女性研究員がこの場所で消息を絶った。
原因ははっきりしない。予告なしに消息を絶つ理由はなかった。
彼女は何らの予兆も見せず、異変の片鱗すらないままに、まさに消えるように行方不明になったのだ。
その後の調査で、これまでに過去 3回にわたって、ブラックドーム内での女性研究員の失踪事件があったことが判明した。
A.G.E.ではこれらの出来事を重く見、ことの真偽を調査するために潜入操作を決行することとなったのだ。
アジアン特有の小柄さ、細身でしなやかな体格、そして若さがもたらす高い運動性能が今回の潜入に適していると判断されたのだろう。
私にとっては初めての本格的な潜入工作。大仕事だった。
緊張と、こういった重要な任務を任されるようになったことへの喜び。
ふたつのイメージを交互に浮かばせつつ、私は作戦を開始した。
潜入は順調だった。
私は厳重な警備をかいくぐってドーム内部へ潜伏し、内部を手早く探索しつづけた。
外部の警戒とは対照的に警備も手薄なラボ内は予想よりもはるかに容易に探索することができた。
そして、カレン教授のプライベートオフィスにまで進入できた私は、そこへ乱雑に積み上げられた資料や書類の束を一つずつ読み取りながら、事件の真相を探っていた。
そして、カレン教授の手記を見つけた。
そこには、失踪した 3人の女性研究員についてのメモが事細かに記されていたのである。
だが、私は失態を犯した。
背後から忍び寄る敵の存在に気づかなかったのだ。
容易さと順調さが、思わぬほどに私を油断させていたようだった。。
あるいはそれは…最初から仕組まれた罠だったのだろうか。
気づいたときには背中に、固い……スタンガン状の物を押し当てられていた。
背後から羽交い締めのように拘束され、悲鳴を上げるべき口を白い布でふさがれたまま、スタンガンのスイッチが入ると、全身に広がる高圧電流の衝撃と、全身の血液が沸騰するような異様な感触と共に、私は意識を失ったのだった。
「そろそろ、お目覚めのようね…?」
耳障りなほどに大きな女性の声。その音に意識を現実に引き戻される。
ひどい気分だ。乗り物酔いをずっと激しくしたような感じで、全身がだるく、腹が重い。
わずかでも身体を動かそうとすると、全身の骨がバラバラになったかのような軋みが走り、思わずうめき声を上げてしまう。
手も、足も、白地の床へ縫いつけたように重く、動かすことができなかった。
「あら。……意外と元気ね、もっと消耗しているものだと思ったのだけれど」
また、頭の中にがんがん、と声が響く。
まるでスピーカーのボリュームを最大にして、それをそのまま耳へくっつけたような感じ…、いや、「~ような感じ」、と表現するのは間違っている。
声そのものが、異様なまでに大きいのだ。
「目を開けて、自分の状況を確認してご覧なさいな、ねずみさん…?」
声は私のはるか頭上から聞こえてきている。
異常なボリュームのせいで、すぐ脇でがなり立てているように聞こえただけだ。
瞼を、ゆっくりと開く。はっきりと意識を止めていなかったため、瞼は重く瞳に被さり、身体の命じるとおりにはなかなか開かない。
時間をかけ、ようやく瞼を開く。
とんでもなく高い天井が見えた。蛍光灯の明かりがまぶしい。光源も巨大なのだろうか、蛍光灯の白色光のはずなのにまるで太陽のようなまぶしさだった。
徐々に明るさに慣れてゆく瞳で周囲を見渡す。
目の前に、一人の女性の顔が見えて来た。
ダークブラウンのくせ毛を長く伸ばしている女性だ。黒いシャツの上から白衣を着込んで居る。
白衣はあたかもおろしたてのような、シミ一つ、皺ひとつない不自然な純白さを保っていた。
彼女が、このラボのオーナー・カレンに違いない。
そこまで認めて、私はある違和感に気づいた。
「まだ、わからないかしら…。もっと、近くへ寄ってあげたほうがいいみたいね……?」
壊れたスピーカーで勢い任せにロックをかけたような、破壊的な音量。
女性の顔が立体感を無視し、視界いっぱいに広がる。
いや、視界いっぱいどころではない。間近に迫ったそれは、唇だけでも横に3mはありそうな大きさだ。
違う。彼女が大きいのではない。
首を巡らせ横を見れば、私の頭のすぐ脇に巨大なクリップが挟まっている。
さらに首をひねれば、ベッドのように私の下に広がっている白い大地にはずらずら、と、一つ一つが50cmほどもあるような大きさの文字が並んでいるではないか。
よく見ると、手足の先がその面に白い液体で固められ、固定されている。…これは、修正液だ…。
もう一度、上を見上げる。
私自身よりも遙かに巨大な唇がにぃ……と妖艶な笑みを浮かべた。
「ふふ……ようやく気づいたみたいね、マウス(ねずみさん)……でも、今の大きさは実験用のハツカネズミよりも小さいわね。……そう、5cm位かしら?」
また、特大の声が響き渡る。
私は、驚愕に目を見開いた。
声を出すことも忘れ、初めて見るように、違和感だらけの見慣れた景色を、あちこちとせわしなく見つめ続けているようだった。
私の身体は、カレンが言うとおりにハツカネズミよりも小さく縮められ、クリップでまとめられた書類束の表に修正液で貼り付けられていたのだった。
「あははははは………っ。ようこそ、私のラボへ……私はプロフェッサー・カレン。あなたを歓迎するわ。」
頭上の巨大な、「生きたスピーカー」から壊れたように哄笑が溢れる。
カレンは、資料の上に貼り付けられた私の目前まで顔を近づけ、わざとらしいしぐさで口を大げさに動かしながら語りかけてくる。
その巨大な口から一言一言が発せられるたびに喉の奥の声帯が震え、まるで振動か突風にも近い音量がぶつかってくる。
耳をふさぎたくても、両手は縫い止められて微動だにしない。
大きく開かれた口腔…唾液に濡れた真っ赤な口内が眼前で妖しく蠢く様子は、カレンの顔全体の美貌とは裏腹に、まるで沸々と溶岩を噴き上げる地獄の釜を見つめているような様子だった。
真っ赤なルージュを引いた唇、白い歯、大きな舌。唾液に濡れてらてらと光り輝くそれらは、身体の奥底から本能的、生物的な恐怖を呼び起こすようで、私は全身をまさしく怯えたネズミのように震わせるだけだった。
「……新開発の “ミニマイザー”よ。ぱっと見はスタンガンみたいだけれどとても高性能で、対象のサイズを1/4から1/100まで自在に変えてしまうことができる。…画期的な発明でしょう? …ふふ…っ」
カレンはポケットから、スタンガン大の装置を取り出し私の前へとかざして見せた。
確かにスタンガンのように見えるそれが、私をこのように縮めさせたのだろうか、そんな荒唐無稽、にわかには信じがたい。
しかし、現実に私は小さくされ、ただの修正液で21cm×29cmの書類の表面へ貼り付けられている。
それは悪夢ではない、現実だ。
私を捕えたことに酔いしれているのだろうか。
心なしか瞳を潤ませ、余韻に浸るような艶やから声色のカレン。
時折品定めをするようにこちらを見据えたり、盛んに唇を舌先で湿らせたりといった動作を見せる。
本来はそれらは、身体の興奮を表すだけのしぐさのはずだ。
だが、そんなカレンのちょっとした仕草にも、恐怖を感じてしまう。
もし、彼女が少しでもその気になれば私は簡単にひねりつぶされてしまうだろう。
修正液で止められただけ。それだけで、溶接されたかのようにびくとも動かぬ手足。
それが、今の私の全力なのだ。
私は、カレンが私を握りつぶすような、そんな気分にならないことを祈るしかなかった。
巨大な顔面を正視していると、身体の奥にじわじわと恐怖が蓄積する。
恐怖に耐えかね叫び声を上げてしまいそうになり、自分を落ち着かせるため、私は、カレンの巨大な顔面から瞳を背けた。
「……それにしても、貴女……エージェントにしては綺麗な身体をしているのね。身長がもっと高ければ、モデルでも通用しそうな位に……」
不意に頬を、いや、身体全体をなま暖かい空気がなでる。
カレンの吐息だ。
背筋を高圧電流のように戦慄が走り、慌てて正面をむき直す。
視界を、巨大な……巨大なルージュが埋め尽くした。ほんの少し、目を離していた隙に彼女の顔は驚くほどに近くまで寄せられていた。
ふぅ……。
目の前で彼女が呼吸をするたびに、私の身体にその吐息が吹きかけられる。じっとりと暖かく、湿り気を大量に含んだ重い空気。
唾液や口内そのものの匂いと、口臭除去剤だろうか、かすかなミントの香り。…それに混じってかすかに漂うのは酸性の匂い。それはカレンの喉を駆け上がってきた人体そのものの匂い…だろうか。
髪の毛に染みいりそうなほどに吐息を浴びながら、私はカレンの瞳を見上げた。
まっすぐにこちらを見下ろしてくる視線に何か、勝者の高揚とは別の……なにか、情炎のような物が混じっているように感じられた。
「ふふ……美味しそうね。とても……」
身体に触れるほどに近づけられた唇から声が漏れる。
全身が総毛立つのを感じた。
脅しではない。
からかっているのでもない。
それはごく自然に発せられた言葉だった。
……喰われる…
そう思った次の瞬間、視界が赤い物で覆われた。
顔、胸、腹、腰……身体の前面が総て、熱く、濡れた肉に包まれた。その塊がぬるぬると蠢き、体表をくまなく這い回り始める。
舌だ。
カレンが書類の表面に縫い止められたままの私をくわえ込み、頬張り、味わっているのだ。
圧倒的な重量、質量、熱、圧迫感…それらが一気にのしかかってくる。
唾液でたっぷりと覆われた、柔らかい、ざらついた表面。
それがぬるぬる、ずるずると、スーツごしに肌の上を這い回る。
巨大なナメクジにでものしかかられているような感触だ。
潤沢な唾液がねっとりと顔面に注がれる。大量の液体は頬や額を犯し、それだけでは飽きたらず、髪へ染みこみ、首を伝い、耳や口の中にまで入り込んで私を覆い尽くしてゆく。
口内へ注がれるものを吐き出そうとしても、口を開けばよけいに注がれるだけだ。
止めどなくあふれる唾液が直接胃や、気管へなだれ込む。
激しい苦痛の中、もだえ、噎せ返る。
舌の表面を通じて揺れるようにかすかな振動が伝わってくる。
舌先に私の苦悶と抵抗を感じて、カレンが忍び笑いを漏らしているのだ。
不意に全身を覆っていた舌がどけられ、視界と空気が戻ってくる。
カレンの口に完全に覆われ、しゃぶられる行為から開放されたようだ。
喉まで入り込んでいた大量の唾液を吐き出し、噎せ返りながら肺に空気を送り込む。
唾液でべとべとに汚れた頬に、涙が流れ落ちた。
だが、終わりではない。
カレンの舌が、今度はその先端だけを使って肌の上を這い回ってゆく。
「っふふ…、柔らかいけど弾力があるわ。舌先をぷるぷると跳ね返してくる……」
私の眼前に開かれた巨大な口腔。
舌先を伸ばしたまま、舌足らずな音色で、湿った、艶のある声が漏れ出す。
カレンはその舌先で私の身体をなぞり始めた。
柔らかい部分を中心に、重い舌先がぬるぬる、と蠢く。
半開きの唇からは、たらたらと唾液が溢れ滴って来て、私の身体の上へぼたぼたと降り注いでくる。
最初に標的になったのは乳房だ。
二つの塊を、まるで転がすように舌先でぐるぐると舐め回される。
肉をえぐられるような圧倒的な質量に、私の乳房は激しく形を変えながら、弄ばれる。
乳房を責められようが、その行為にセクシャルなものは感じるはずもない。
乳房と肋骨越しに肺を圧迫され、あらかたの空気を吐き出してしまえば呼吸も出来ずむせ返り喘ぎを漏らすだけだ。
楽しんでいるのはカレン。私はその悦楽のための玩具に過ぎない…。
舌はやがて臍の周りや、下腹部を蹂躙しながらゆっくりと下ってゆく。
舌先だけでも、私の胴回りよりもはるかに太い肉塊だ。
その凶器で腹部を押されれば、そこへ収められた内臓が口から飛び出しそうになり、私はカレンの舌で絞り出されるように幾度もうめき声を上げる。
その声を聞くたびにカレンはわずかに舌先を浮かせ、喘ぐように呼吸を求める私を見つめては、それに高揚させられたようにぬらぬらと舌の表面に新たな唾液をたっぷりとにじませるのだ。
やがて、執拗な責めは脚の付け根へとうつる。
槍のようにとがらせた舌先に、たっぷりと唾液をしたたらせると、それで膝頭を押し開き、腿の内側から、その奥の秘所までを丹念に舐め回すのだ。
ぬるぬるとした感触が下方から這い上がってくる感触は想像を絶し、舌先が股根をつついて来ても嫌悪を感じるだけだ。だが、その表情とうめき声が、カレンにはたまらなく甘美に写るようだった。
身体にはきかけられる呼吸が荒くなったと思うと、舌が股間から胸まで一気に這い上がる。
身体の表面、柔らかな部分を強くなぞり押し上げられて、喉奥から悲鳴と共に泡混じりの唾液が飛び出した。
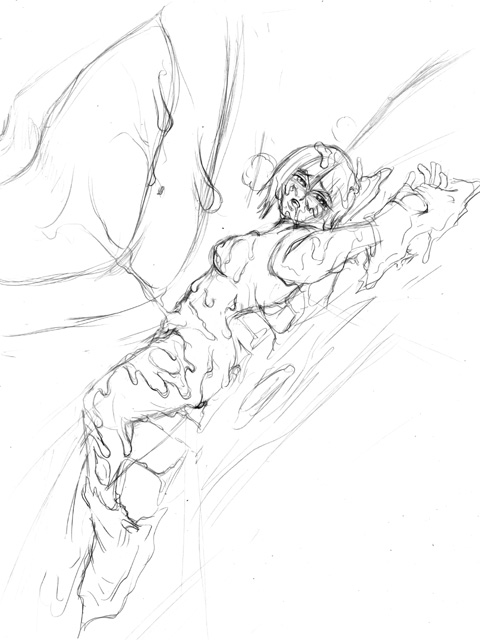 カレンはこちらの苦悶などおかまいなしに、胸から股間、内腿から喉もとと、幾度も舌を滑らせ繰り返し、繰り返し私の身体を味わう。
カレンはこちらの苦悶などおかまいなしに、胸から股間、内腿から喉もとと、幾度も舌を滑らせ繰り返し、繰り返し私の身体を味わう。
途中、何度もカレンと視線が合った。
その瞳に浮かぶのは、理性的な輝きに巧妙に覆い隠された、捕食者の残虐な嗜虐心に満ちた歓喜の表情だった。
どれだけ時間が経ったのかもわからない。
ようやく十分に舌触りを堪能したのだろうか、カレンの顔が不意に遠ざけられた。
そのころには私はすでに、全身…胸側どころでなく背中側までもが、執拗に塗りつけられた唾液の層に染み、ねっとりとした感触で完全に覆われていた。
髪の毛一本一本にまで染み渡った唾液から立ちこめるもうもうとした湯気の向こうに、疲弊しきった私を見つめる一対の瞳と、真っ赤な唇を濡らし舐めあげる舌が見える。
瞳も、舌も、存分に私を陵辱しつくした歓喜に満ちているようだった。
「本当に……いい味。今までこの研究所で捕まえたどのエージェントよりも素敵な舌触り……今すぐにでも丸ごと、味わってしまいたい位……ふふ…っ」
カレンが艶めかしい声を上げる。
その声色は、先ほどからずっと同じ。
冗談めいた響きにはほど遠い、とろり…と情欲にとろけるような声だ。
この狂科学者ならば…ためらうことなく私をその口に飲み込んでしまうだろう。
そう……一口で。
童話の赤ずきんや、一寸法師のように。
自分の身体が、あの巨大な唇にくわえ上げられ、ゆっくりと、呑み込まれてゆく様が脳裏をよぎる。
全身の毛が逆立った。
「この、丈夫なスーツがとてもじゃまね…」
私の恐怖などよそに、カレンが再び顔を近づけてくる。
急に、私の身体が熱い感触に包み込まれた。
カレンが唇を大きく開いて、私をくわえ込んだのだ。
つい先ほど想像したばかりの光景が脳裏をよぎり、私は胴を左右へよじり、腰を跳ね上げ、膝を震わせ必死にあがいた。
意味のないことを必死で叫び立てながら。
この熱い、赤い、湿った牢獄から逃れたかった。
筋肉が緩んだ。股がじゅっと熱くなった。暴れながら失禁したらしい。口内の熱とは違う熱さが股間を中心に、スーツの内側を、臍の下と尻と脚のほうへ広がった。
ふ…っ、と大きく鼻息が漏れる音が響いた。
私の往生際の悪さを、なりふり構わぬ抵抗をせせら笑ったのか。
それとも…スーツの内側に広がった粗相を舌先に感じて侮蔑の笑みを漏らしたのだろうか。
私を完全に包み込んで、肉体を挟み弄んでいたカレンの口。
その唇の一層内側に並ぶ歯…一つ一つが1m以上もあるような巨大な石臼が、私の上下から噛み合わさり、重圧をかけてきた。
たちまち全身をとてつもない圧迫感が襲う。
唇や舌での圧迫とは質が全く異なっていた。硬い歯の表面に触れ合う場所がぎしぎしと軋みを上げ、意識をしっかり保とうとしなければ、今すぐにでも失神してしまいそうなほどの激痛が走る。
カレンにしてみれば、悪戯に甘噛みしているようなものなのだろうが、それだけでも私の全身はバラバラにされてしまいそうだ。
つぶれたチューブから絞り出されるように肺の奥からしわがれた悲鳴を漏らし、かろうじて自由に動く頭を激しく振る。
その、何の変化ももたらさない悶絶だけが、私にできる精一杯の抵抗だった。
噛みつぶそうとでも言うように身体を挟み込んで居た歯が、身体の表面を滑り始める。
今度は歯先で私の全身を味わおうとでも言うのか。
歯は腹部をなでつけるように滑ると、不意に、私の身を守るスーツの薄い布地を挟み込んだ。
ぎち…っ
嫌な音がし、柔軟なスーツの生地が勢いよく引っぱられる。
急激に引っぱられた布地が腋や、股間に食い込み、全身の筋肉が布地と一緒にねじれ、強く引っぱられる。
私は、がらがらに嗄れきった喉で、もう何度目かもわからない苦痛の悲鳴をほとばしらせた。
カレンが歯で、スーツを喰いちぎろうとしているのだ。
力任せに引っぱりながらぎしぎしと歯をすりあわせ、スーツを噛みちぎろうと、引きちぎろうとする。
伸縮性・耐久性の高いスーツは持ち前の粘りと強度を発揮し、破られることはなかった。
だが、引っぱられねじられることによる痛みは避けようがない。
カレンが歯をきしらせるたび、そうすることで奏でられる楽器のように、私は肺から悲鳴とも空気が漏れだしたものともつかない声を漏らす。
苦痛で、叫ぶ気力すらも失われているのだ。
「……ほんとうに丈夫よね。歯でこんなに噛んでいるのに、穴一つあかないなんて」
やがて、スーツの丈夫さにあきらめたのか、布地を引っぱり拘束していた歯がゆるみ、私は開放された。
開放されたと言っても、身体はもはや力を失い自由に動くことなど一切、ままならない。
唾液が染みて、ふやけきった紙の表面に四肢を縫いつけられた姿勢で、腹を激しく上下させ、ぜえぜえと嗚咽まじりの粗い呼吸をつくだけだ。
視界はぼやけ、意識は朦朧とし、目の端からは涙が止めどなく溢れ出す。
荒い呼吸のまま、紙面に大の字に固定されたまま、ぼやけた視界でカレンを見上げる。
彼女は、唇を盛んに舐め上げ、そこを指でなぞりあげ、そこへ残る私の身体の余韻に酔いしれている様子だった。
人を玩具のように弄び、食物のように味わい、その味に恍惚とする…。
噂以上の狂科学者だった。
洪水のような震えがとめどなくあふれ出して来て、止めることが出来なかった。
こんな気分に囚われたのは生まれて初めてだった……。
怖い。
……怖い。
「いい表情ね……喰われることに怯える動物の目。……もっと…遊びたくなってしまう……」
…ひっ…
私の視線をめざとく見咎めたカレンが舌先をくねらせ伸ばす。
顔も近づけるわけでない、たったそれだけの行動だというのに、私は少女のように悲鳴を上げ、視線を下げてしまう。
カレンはそんな私の様子を見て、伸ばしていた舌を口内に納めると満足げにふう、と一息をつく。
「あはは……上出来よ。貴女は、意外と素直なのね。……そう、獣はより大きなものには逆らえない。被捕食者は捕食者に反抗することができない。なぜなら、本能にそう、刷り込まれているからよ。」
気が遠くなるほどに巨大な美貌が、くすり…と鼻を鳴らして笑う。
反論する余地はなかった。
全身に唾液と苦痛だけでなく、逃れようがない恐怖も刷り込まれていた。
頭上で開閉する巨大な口腔が視界にちらつくと、それだけで身体に力が入らなくなる。
腰が抜けるというのはこう言うことなのか ……。
「でも、あんまりそうやって私を誘惑しないでくださるとうれしいわ…。貴女には特別の、楽しいコースを用意したのに…そんなこと忘れてこのまま食べてしまいたくなるもの……」
くす、くす……。押し殺したような、忍び笑いが盛んに漏れる。
もちろん、誰も誘惑などしていない。
カレンが……勝手に、興に乗っているだけなのだ。
だが反発したくても、喉は嗄れ、渇き、貼り付き、声を発することができない。
カレンが、やや落ち着いたような、むしろ、作ったように事務的な仕草で私が縫い止められている書類を手にとった。
大地が垂直に傾き持ち上がる厭な感触。そして猛烈な浮遊感。
恐怖に怯えた身体は、どんな刺激にも萎縮し、全身は震え小さく縮んでしまう。
そのまま私は、デスクの上を離れカレンの視線の高さまで持ち上げられた。
こちらを見つめる一対の巨大な瞳。
そこへ宿る猛禽の輝き、獲物…餌を見る肉食獣の輝きが私をとらえる。
私は、萎縮し……その瞳から目を離すことができない。
蛇に睨まれた蛙……まさに、その状態だ。
「貴女には特別のコースを用意しているのよ。…この研究所から新しく誕生する、すばらしいバイオテクノロジーの体験コースなの…」
カレンはそんな私の状態には構わず、まるで訓練された女優のようなはっきりとした理性的な声調で言葉を継いだ。
獰猛で、貪欲で、残酷な獣がその本性を隠すために煌びやかで美しい仮面を被る。……そんな感覚がした。
体験コース、という単語に、背筋がぞろり、と粟立つ。
そのコースは、間違いなく体験する者を楽しませるような物ではない。
彼女自身、自らのゆがんだ欲望を楽しませるのプログラムだ。
人間を「美味しそう」と形容し、ガムのようにしゃぶり味わい恍惚を浮かべる狂った頭脳を満足させるような、特別のコースなのだ。
カレンの左腕が、先ほどまで私が乗せられていたデスクの脇へとのびた。
そこに並ぶいくつかのスイッチの内のひとつを押すと、デスクの端に大きく、丸い穴が開く。
ダストシューターだろう。書類を整理するための装置だ。
普通なら、この穴は鋭利なシュレッダーへとつながっていて、廃棄した書類から機密が漏洩するのを防ぐために、投じられたものを粉々に切り刻む。
……彼女はそこへ私を放り込んで処分するつもりなのか。
そんな、単純な手段でこの貪欲な獣の心は満足すると言うのか。
信じられない。
一瞬、身体を硬くし、身構える。
「怖がらなくても大丈夫よ。すぐには死なないもの。すぐに死んでしまっては『体験』コースにならないでしょう?」
私の反応を見て、カレンが唇を三日月の形にゆがめた。
ちょっとした私の反応でも、彼女にとっては殊の外満足を与えるものらしい。
彼女にとって、恐怖や緊張を簡単に顕わにする私はひどく「お気に入り」の獲物、ということだ。
「このシュートは、研究所の地下にある生命研究区画へつながっているわ。貴女がこれから行くのは、わたしが最近開発したばかりの、遺伝子改良で身体能力を高めた画期的な畜産牛のところ。身体も大きく、成長も早く、肉は美味、そして一番の利点は育てるための餌を選ばないこと…。」
ただ、一様に事務的な作り声で奏でられる解説。
畜産牛と、ダストシューター。
私は、困惑した。
「消化能力を強化されたバイオ牛だから、オフィスから出る廃棄書類でも飼育できるのよ。貴女には、その画期的な消化能力を体験してもらうことになるわ…」
ダストシューターのホールの上で、書類をつかんでいたカレンの右手が開かれた。
私の身体は、支えを失った書類と共に丸いホールに吸い込まれる。
急速に流れる視界、遙か上方に丸く、オフィスの光が見える。
そこから、覗き込んでいるカレンの顔が見える。
笑っていた。……これから私が体験する事をすべて把握し、その想像の中で、彼女の期待通りの反応をする私を描き、そのイメージで、エクスタシーに染まっている表情た。
消化能力の体験…?
書類を餌に、飼育できる牛…?
つまり、私は。…私が貼り付けられている書類は…
牛の餌に…
「ゆっくりと楽しんでね。『幻想的な航海』のコースを……」
最後の、思考……それが結論に替わる前に、私は落下に屈し、闇に意識を奪われた。
どさ。
背中に強い衝撃を感じ、目を覚ます。
まぶしいほどの光が上から照りおろしてくる。
かすかにうめき声を上げながら、私は四肢を身体へ引き寄せようとした。
動かない。
すぐに、手足は拘束されていたことを思い出す。
一つ思い出せば、すべてがはっきりと記憶によみがえる。
私は、狂った科学者カレンの手によって5cmにも満たない大きさに変えられ、ダストシューターに投げ捨てられたのだ。
………そして、彼女の計画ではこれから…
記憶をたどるためにぼう、としていた視界に巨大な影が飛び込んでくる。
巨大な肉の塊、その内側に並んだ白い岩のような列。
それが私のすぐ脇をかすめる。
反射で身体をかわすことも、萎縮する暇すらも、与えられない。
あっという間に、私は落下してくる白い岩と岩の列の間に閉じこめられてしまった。
そして気づいた。
これは口だ。
カレンが自慢げに語っていた牛の、口なのだ。
脳内に、自分が置かれている状況のシミュレーションがめまぐるしく駆けめぐる。
ダストシューターをくぐり抜けた書類は、研究所の地下施設にあるバイオ牛の厩舎へ放り出される。
落下するのは牛の飼料桶だ。新種の牛は草どころか、不要になった書類などの紙くずを飼料がわりに飼育できる。
腹を空かせていた牛は、目の前に現れた真新しい餌を見て涎を飛び散らせながらそれに食いつく。
そして口いっぱいに、ごちそうを頬張るのだ。
そして、私が居る場所は……その資料。
牛が頬張った「御馳走」の1ページ目の表面なのだ。
逃げる暇もないままに、私はすでにカレンの特別コースの第一ゲートをくぐり抜けていたということだ。
巨大な牛…正確には私が小さいのだ。牛が大きいわけではない……は私と資料を頬張るとその口を閉じたようだ。
背中の遙か下方でごつん、と歯が噛み合わさる音がし、わたしは暗闇の中に囚われた。
周囲は紙とインクと、唾液の放つねっとりと臭気に満ちていた。
すぐに、天井の方向からぼたぼたと大量の液体が落ちてきて、私の身体をぐっしょりと濡らす。
それは生暖かく、ぬるぬると執拗に身体にからみついてくる。
牛の唾液だ。
唾液はカレンのものとは全く比較にもならないほど量が多く、ものの2秒とかからないうちに私の身体は濡れるどころか唾液の海に溺れるような状態となった。
全身余すところなくぬるぬるとした粘液の海に囚われる。量だけでなく粘りけも強い。身体の横や背中の下をずるずると流れる唾液は、まるで意志を持った粘液のように身体の表面を撫で、そこへ染みてゆく。
やがて身体が急激に持ち上げられる感触が襲う。
つづいて、ほぼ同時と言ってもいいような速度でとんでもない横揺れが襲ってきた。
牛が咀嚼を始めたのだ。
私はなすすべも持たぬままに大量の唾液に溺れながら、横揺れと縦揺れが激しく入り交じった嵐の中へ晒されていた。
まるでミキサーにでもかけられている感じだ。
そうでなければ洗濯機だ。
業務用の巨大な洗濯機で洗われればこんな状態になるだろう。
熱、粘液、肉、柔らかく熱く絡みつき染みこみ、急速に、確実に抵抗を奪うものに支配された口内で、ただ、もみくちゃにされる。
時折身体の側でごつ、ごつ…ごり、と硬質のものがぶつかり合い擦れるような鈍い音が鳴り響く。
嵐に晒される身体のすぐ横で、牛の歯が噛み合わさり餌を噛み砕いているのだ。
挟まれれば命はない。
いつの間にふやけてしまったのか、手足の拘束はゆるみ、その効力を失っていた。
私は真っ暗な牛の口内で手足を丸め、膝を抱えた姿勢になりながら必死で、咀嚼の嵐に耐えていた。
唾液が完全に染みこんだ身体は何もつかめないほどにぬるぬるだ。
ぬるぬるとしているから、どんな揺れでも大きく滑り、止まることがないのか、と思うほどにあちこちへと振り回される。
耳の真横……本当に1ミリほどの横でごり、と歯が擦り合わさる音がした。
緊張が極限に達し、私は口を開けて悲鳴を上げた。
実際には口内にも粘液がたっぷりと詰まっていて悲鳴など上げられるはずはない状態だったが、私は意識の上で必死に叫びをあげていた。
もう一度、失禁していた。それも気にしてはいられなかった。
股から溢れた尿水が、スーツと皮膚の隙間の狭い空間へしょろしょろ、と広がっていった。
やがて、身体が急に高く持ち上げられた後、私と、私を覆う唾液やかみ砕かれた餌の混じった沼泥とが深みへと押し流される。
牛にとっては私は、ただ飼い葉桶に放り込まれた餌の一部だ。
口に入れた餌を吐き出す訳がない。
…嚥下。
私は呑み込まれる。
すっかり縮み上がった身体で、膝をぎゅ、と抱える。
噛みつぶされなかったのは奇跡だ。
だがそれははたして喜ぶべきことなのだろうか。
むしろこれは、カレンの意図通りの展開なのではないだろうか。
生きたまま、噛みつぶされもせず、彼女の開発したバイオ牛の体内へ送り込まれる。
……そして、彼女が設計したその体内を『体験』するのだ。
私の身体は泥濘とした食塊と共に狭い肉の管の中を深く、深くへと運ばれてゆく。
周囲を覆う、粘膜で包まれたなめらかな筋肉の壁が上下から私を挟み込むように収縮し、蠕動を繰り返しながら、私の身体を下へと押しやる。
全身を覆う粘液のせいでほとんど息ができない。
周囲を取り囲む肉壁がぶるぶると震えながら私を締め付けてくる。
意識が徐々に朦朧としてきた。
はっきりしない意識、酸素を求める苦痛の中で、その蠕動の波が訪れるたびに、私は引き返すことのできない一本道を、巨大な牛の体内へ向かって押し運ばれていることを漠然と感じていた。
下へ、下へと向かっていた肉壁の傾斜が緩やかになってくる。
熱い肉にすっぽりと包み込まれた身体に、壁越しにどくん、どくんと鈍い振動が伝わってきた。
……おそらく心臓の音だろうか…。
心臓の近くを通れば、まもなく終着点だ。
私の身体はしばらくの間ほぼ水平に運ばれると、やがて、ひときわきつい締め付けを見せる肉のリングに捉えられた。
リングは一度、収縮して私の身体を受け止めると、ゆっくりとその口をゆるめ、私を脚から迎え入れる。
長いとも、短いとも判断しかねる体内への一本道の終着点だ。
ここで食道は終わる。
この筋肉の門が、噴門だ。
身体が半ばまで受け入れられたところで、周囲の筋肉がひときわにきつく収縮し、私は絞り出されるような勢いで広大な空間へと押し込まれた。
粘液でじっとりと湿った肢体は肉壁の束縛から放り出され、しばし宙を舞った後に、空間の底へわだかまるどろどろとした粥のような粘液の沼へ受け止められた。
どろどろの泥沼はどぶり、としぶきも上げずに、私の身体を受け止める。
重く四肢を捉える粘流を振り切り、呼吸を求めて、沼の表面まで身体を浮かび上がらせる。
顔をべっとりと覆い尽くしていた粘液を掌で振り払い、生暖かく、生臭い空気を肺に出し入れする。
空気は湿気を含んでいて、水の中で呼吸するような厭な感触だったが痛いほどに酸素を求めていた肺には少なからず新鮮なものには違いなかった。
とうとう、終着点へたどり着いてしまったのだ。
ここは胃の中だろう。私が浮かんでいるどろどろした粥状の沼は胃液と、牛の餌が混じってできたものだ。
私もすぐにこの粥のように溶かされる…。
ごろごろ、と液体が巡る音、ぐりゅ、と消化器官が蠕動する音、びちゃびちゃと、消化物が混ぜ合わさって流れる音が立ちこめる。
生臭い臭気と、不気味な液状の音、そして暗黒の支配する体内。
私は瞳を閉じ震える身体を自ら抱きしめた。
少ない酸素で半ば揺らぐ思考は、終焉を待つ生贄の心地を伝えた。
「いらっしゃいませ。本日はカレンズラボの最新アトラクション『幻想航海』体験コースへのご参加、ありがとうございます! わたしはツアーの案内役を務めるプロフェッサー・カレンです。どうかお見知りおきくださいませ!」
唐突に、場違いに明るい、まるでバスツアーのガイドのような調子の声が牛の体内に響き渡る。
その声は確かにカレンのものだ。間違いなかった。
慌てて左右を見渡すが、明かりすら届かぬ体内では何も見えるはずもない。
「このコースは、当研究所で新開発されたバイオビーフの驚異的な消化能力を、飼料の立場になって実際に体験して頂くコースなの。とても素敵でしょう? …ふふ…っ…。 すでに修了した、咀嚼と嚥下のメカニズム体験はいかがだったかしら? ……コースはまだまだ続くから安心してね。……その表情では、もう今すぐにでも消化されてしまうと思いこんでいるみたいだけれど、ね。……くす…くす…っ」
まるで私の表情がずっと見えているかのような語り口調だ。いまにも忍ばせ切れないと言った様子で盛んにくすくすと笑いをこぼすカレン。
私は、真っ暗な体内で消化物の粘流をかき分けながら声の発生源を探し始めた。
声は意外に近くから響いている。牛の心音よりも内側から響いているからだ。
つまり、牛の外側から語りかけたりしている訳ではない。
だが、カレン本人が牛の体内まで出向いているとは考えられない。
それは自殺行為に等しい。
「もっと顔をよく見せてもらえるかしら。……ああ、いいわ。よく見えるわ。…わかる? このバイオ・ビーフ…ああ、『ビーフ』では食肉になってしまうわね。この場合の食肉は貴女の方だから、バイオ・カウとでも言わないとおかしいわよね? あはは…っ……ふふっ……。…この牛には、貴女を食べさせる少し前に極小のカプセル型カメラを呑み込ませてあるのよ。貴女の表情を見ながらコースの案内ができるように、ね。…私の案内メッセージはすべて、そのカプセルに内蔵させたスピーカーから届けているわ。……貴女のすぐそばにあるはずだから探してご覧なさい? くす……ふふ…っ………あはは」
どろどろとした粘液質で埋め尽くされていた体内で、ひときわ異彩を放つカレンの声。
心底、悪趣味な趣向だ。…本気で、私の体内での消化体験コースを案内するつもりで居るとでも言うのだろうか。
その耳障りな笑い声を止めてやろうかと、泥沼をかき分けカプセルを探す。
床全体、私が納められている胃袋全体をゆるやかな蠕動がかき回している。
そのため、粥の沼地には常に緩やかな波が起こっていて、ただでさえ重い水面を掻き分けて進む行為は困難を極めた。
だが、目指すカプセルはすぐに発見できた。
常にカレンが作り声でナレーションを垂れ流していたからだ。
全長6cmほどなのだろうか。私よりも一回り大きなカプセルには丁寧にも、小さくなった私が捕まれるような取っ手がしつらえてあった。
これが、私のこれからの旅路の案内役、ということか……。
「ビンゴ! おめでとう。…カプセルの頂点付近を探してみて。ライトのスイッチが見あたるはずよ。それとは反対側のサイドには新鮮な酸素がたっぷり詰まったマイクロタンクが入っているわ。体内旅行を楽しむための、私からのプレゼントよ。気に入って頂ければうれしいのだけれど! ……あははは」
カレンは最初から、侵入者をこの方法で弄ぶつもりで居たのだろう……あまりに、手際が良すぎる。
ひどい屈辱を感じたが、酸素も光もこれからの私には確実に必要になるものだ。反抗することはできそうにもなかった。
沼の底の方を手探りして酸素のチューブを手繰り寄せた。
乱雑にチューブの口についていた粘液を払いのけ、口に咥えて酸素を吸い込む。
湿った空気とは全く違う新鮮な空気が肺に満ち、ぼやけていた意識が急にはっきりとしてきた。
次に言われる通りに、ライトのスイッチをさぐりあて点灯させる。
目がくらむような閃光とともに、バイオ牛の体内が煌々とライトで照らし出される。
 映し出された光景に私は一瞬、声を失った。
映し出された光景に私は一瞬、声を失った。 広い…。とてつもなく広いというのが最初の印象だ。
まるで巨大なタンクの底から見上げているような感じで、視界いっぱいに胃の内壁が広がる。
ザラザラとした突起に覆われた胃の表面は分泌されている粘液でてらてらと照り輝き、ゆっくりとした蠕動が、壁面に反射する光のテクスチャをゆるやかに変化させ、ビロードか何かのような妖しい輝きを作り上げている。
私と、カプセルが浮かんでいる消化物は白と緑色と土色の三色が入り交じった奇妙な色合いだ。
蠕動によって盛んに混ぜ合わされた粥状の湖面は、所々でぶくぶくと泡だち、びちゃびちゃ、と飛沫を立てている。
その沼に浸っている自分の身体が、脚の方から今にも溶け出してしまうような錯覚にとらわれ、私は冷や汗をかきながら足先を手探りで確かめた。
カプセルカメラを通してすべてを見つめているのだろう。カレンがまた、忍び笑いを漏らす。
「大丈夫、簡単には消化されやしないわ。……今貴女が居るのはこの消化体験コースの第二プログラム。牛の第一胃と呼ばれる場所よ。牛は大量の草を消化する。草のように固くて消化しにくいものが主食なのになんであんなに大きな体を作れるのか……その秘密がこの第一胃に隠されているの。」
捕まっているカプセルの中からカレンの解説の声が響く。
圧倒的な景色に気を奪われ、粘液に消化される錯覚に恐怖する私をよそに、解説はゆっくりと続けられた。
「牛の第一胃には、消化液の代わりにたくさんの細菌が居るの。そしてアルコールの貯蔵樽のように、内部で細かくすり潰された餌を発酵させて、消化しやすい状態へと変質させているのよ。…ここは、つまり、巨大な貯蔵工場であり、同時に食べたものを消化するための準備を行う加工工場でもあるわけね…」
細かい説明は、どうでもよかった。
つまり、すぐに溶かされてしまう危険性はない…ということだ。
私は唾液や体内の粘液で汚れた顔を念入りに手のひらで拭い、カプセルを脇に抱えるような姿勢で粘流を掻き分け、巨大な体内のタンクの中を探索し始めた。
カレンの作ったような美声と、極端に場違いな解説とが、私の心を何とか落ち着かせてくれた。
どうにかしてこの、逃げ場のない牢獄から抜け出す方法がないものか…。
消化物を掻き分け、壁面まで泳ぎ着く。
この壁面をよじのぼることができれば、あるいは…
「まじめな表情になってしまってはつまらないわね…。でも、そうやって焦ってあまり胃壁を刺激するといいことにはならないわよ? …くす、くす……っ」
その私の様子を観察していたらしいカレンの、笑い混じりの声が響く。
そして、その言葉が表す事柄を、すぐに私は体験することとなった。
突然壁面がぶるぶると震えだしたと思うと、胃全体が激しく震え始める。
今まで緩やかに波立ち、攪拌されていただけの湖面が一気に逆波だった。
唐突に、激しい蠕動運動が巻き起こったのだ。
私は、カプセルと一緒に、たやすく激流の波間に呑み込まれ、嵐を漂う木の葉のように翻弄される。
「カプセルにしっかり捕まるといいわ。…酸素のチューブをくわえて、口から離してはダメよ? くすくす…いいわ、その、必死な表情…。死に直面した恐怖に引きつった顔。…たまらない…もっと必死になって見せて? あは…あははっ…………あははははははは……」
反論をしてやろうと言う気持ちさえ起こらない。
少しでも気を緩めればカプセルの取っ手から手をもぎ離され、この粘流へたやすく呑み込まれてしまう。
なのに幾度となく繰り返される激しい波に体力は奪われる一方だ。
何度も、身体をはがされそうになり、必死でカプセルをたぐり寄せる。
いや、むしろカプセルに身体をたぐり寄せると表現した方が正しいのかもしれない。
揺れと大波の中で必死に身体を、カプセルのつるつるした、卵形の、丸い表面に密着させる。
両手を回して抱き込むようにし、両足もくっつけて、卵の表面にしっかりと捕まるのだ。
そうしたら、波にもまれる身体が比較的、楽になった。
とは言っても揺れが治まるわけではない。
酸素のチューブは、歯型がつくほどにしっかりと歯でくわえ込んだ。
激しい揺れは寄せたり引いたりを繰り返しながら、カプセルと私を翻弄し続ける。
まるで天井に向かって、真っ逆さまに「落ちる」ような感覚がずっと続き、三半規管の混乱でひどい気分だ。
自分では覚えていないが、何度か周囲の粘流に、自分の胃の中身を吐きだしたかもしれない。
気づけば、口元にチューブの感触がなくなっていた。
喉の奥がひどく荒れた感じがした。
気づけば、ずっと全身を翻弄し続けていたうねりはほぼ、おさまっていた。
私は幾分量の減った「浅瀬」らしい場所へ打ち上げられていた。
身体を覆うどろどろの消化物にまじって、背中に、ざらざらした壁面の熱とじっとりとした感触を感じた。
頭をぶるぶると揺すって意識をはっきりとさせる。左右へ首を振るたびに、髪の毛にぐっちゃりと染みこんでいた粘液やどろどろの繊維が飛び散る。どろどろの頭は普段の何倍もの重さがあり、首が疲れる。
そうして少し落ち着きを取り戻してから、ふ、とライトに照らし出される周囲の状況を見やってみた。
なぜか、ひどく胸騒ぎがする……。
最初に視界に写ったのは天井だ。
先ほどまでとは異なり、表面に一切の繊毛が生えていない天井は見た目、かなり固そうな印象だった。
それは胃カメラの画像などで見る胃壁とも違う。
なにかもっと、頻繁に見覚えがあるような、そんな感じの壁面だ。
そのまま視線を下ろす。
視界に、規則正しく立ち並ぶ白い巨大な岩塊が映し出された。
……歯だ。
それは間違いなく牛の歯だった。
なぜ。
私は、ついさっき、確かにこの場所を抜けて牛の胃に呑み込まれたはずなのに……
「ファンタスティック! おめでとう。……このコースで『反芻』を実際に体験できるのは本当に珍しいことなのよ? 貴女は運がいいわ、今年最初のラッキー・ガールは貴女で決まりね? くす、くす…っ」
カレンの声。
私は軽く、納得のうなりを漏らした。
そうか……反芻。牛は呑み込んだ食べ物を口の中へ戻して繰り返しすり潰す習性があった。
背中側、大地がゆるやかに動きはじめる。
私は牛の舌の上に仰向けに寝かされている。牛が反芻した食物をゆっくりと、咀嚼し始めたのだ。
周囲に蟠る、細かくすり潰された繊維の粘液が牛の歯の間へ流し込まれ、白い巨大な歯が石臼のようにごりごりと擦り合ってそれをさらにこまかくかみ砕いていた。
最初の時に比べれば、その動きはゆるやかで、私は噛みつぶされる恐怖にさらされることなく、しばらくの間その咀嚼を見学することができた。
牛の歯がダイナミックにこすれ合い、緑から黄茶色に変色しつつある粥泥がゆっくりと噛みつぶされてゆく。
咀嚼行為に刺激されたのだろう。舌の裏側からねっとりとした唾液が大量にしみ出してくる。
私の身体は再び、熱い粘液のプールに徐々に浸されつつあった。
時折、せわしく開閉する歯と歯の隙間から明るい光が漏れてくる。
物を噛んでいる間も口が半開きなのだろうか。
3,4度、ぼうっとその光を見つめていたが、不意にはっとなった。
今、その隙間から飛び出せば私はこの地獄から抜け出すことができるかもしれない。
にわかに、血液の巡りが沸騰する感触が沸きあがった。
脳内物質が急激に分泌され、どくん、と心音が跳ね上がるのを感じる。
どうやらカレンはスピーカー越しに、反芻のメカニズムを熱心に解説しているようだ。
詳しい内容などは耳に入らない。
舌の表面に身を起こし、膝立ちの姿勢になって慎重にタイミングを計る。
歯は規則正しいリズムで開閉し、食物をすりつぶしている。だが、その隙間が十分に開くタイミングはあまり長くなかった。
何度か、タイミングを計り……跳躍に備える。
3……2……1……
ぐら。
いきなり、足場が揺れた。
牛が急に舌を大きく蠢かせたのだ。私はバランスを失い横ざまに肉の断崖を転がり落ちる。
粘液の糸を引きながら、落下……上半身を固い物に衝突させ、衝撃と痛みに声を上げる。
私は必死で、ぶつかった物に腕をからめて落下を食い止めた。
ぐらぐらする頭。瞳を閉じる、ばらけた意識をひとつにまとめる。
目を開く。
私が乗り上げているのは、牛の巨大な臼歯だった。
頭上から、背中に敷いているのと同じ大きさの臼歯がゆっくりと降りてくる。
今の私にとっては歯、などという生やさしい代物ではない。
直径3,4mにもなろうかという巨大な石臼だ。挟み込まれれば小さな私の身体は容易く砕かれてしまう。
もし即死を免れても、胴を噛みちぎられればその後、石臼のような上下の歯の隙間で挽肉のようにすりつぶされ、苦痛で死ぬのが先か…身体の機能が停止するほうが先か……。
この場所から早く逃げなければ……。
唾液が身体に絡みつく、満足に動くことができない。
焦りと、ショックが、よけいに手足の動きを遅くさせる。
だが、大量に分泌しているであろう脳内物質が意識と視界だけをはっきりとさせる。
大きく……大きく見開かれた瞳に映る光景はゆっくりと、スロー再生のようにゆっくりと迫る惨劇までの時間を映し出すのだ。
白い、巨大な歯が降りてくる。
視界は真っ白い、でこぼこした凹凸の浮かぶエナメル質の表面で埋まる。
あとどれくらい降りたら、私の身体ははさみ込まれるのか。
3m……2m……
不意に、視界の半分を丸い物体が覆った。
…カメラのカプセルだ。
咄嗟に腕を伸ばし、カプセルの取っ手を両手でつかむ。
腕の力だけで身体を引っぱり、自分と、カプセルの、位置を入れ替えた。
だが、下半身がまだ、死のプレスの範囲から逃れ切れていない。
もう少し、もう少し…………
ごりっ……。
とてつもない音が鳴る。
背筋を冷たい血液が逆流し、駆け上がるのに合わせて全身の毛穴が開くような感触が伝わる。
「ワォ、危機一髪ね……?」
牛の歯は、その間に挟みこまれたカプセルのために完全に閉じられることはなかった。
歯の上に残っていた私の脚も、カプセルが作ったわずかな隙間のおかげでかろうじて惨劇を逃れていた。
開いた毛穴から、どっと冷や汗が吹き出す。
魂が抜ける思いで私は脚を、歯の隙間から引き抜いた。
牛が、異物をかみ砕こうともう一度歯を開くのに合わせて、カプセルを引っぱり寄せ、もう一度舌の中央に身体を寝かせる。
舌がゆっくりと持ち上がり、私の身体は舌と天井にぴっちりと挟み込まれた。
どうやら、咀嚼を終えた食物と一緒に、私はまた呑み込まれるようだ……。
カプセルに両腕を回し、しっかりと身体を密着させると、私はゆっくり瞳を閉じた。
牛は、ごくり、と喉を鳴らし、一層どろどろになった繊維の粘流と一緒に私の身体を食道へ、送り込んだ。
2度目の嚥下に合わせて私は意識を失ってしまっていたらしい。
ふ、と瞳を開くと、私は見慣れない臓器の内部にいた。

いままで私がいたもののように表面を細かい絨毛がびっしりと覆い尽くしているものではなかった。
「おはよう。お目覚めは快適かしら? 2回目の反芻が体験できなくて残念だったわね。……貴女は眠っている間にまた一つ、体内ツアーのゲートをくぐってしまったのよ? ……貴女が今いる場所は第二胃。発酵の進んだ食物が蓄積され、次の胃へ送られるのを待つ場所。…通称『蜂の巣胃』とも呼ばれる静かな場所よ」
もうすっかりとおなじみになってしまったカレンのガイドが訝しむ私の耳に解説を挟んでくれた。
なるほど。…言われてみれば確かに襞状の壁面でブロックのように区切られた内壁は蜂の巣に見えない事もない。
…それが生暖かい肉壁で出来上がっていて、呼吸し脈動するたびにぐにゅぐにゅとうねりを伴って動く壁でなければだが。
「大分、このツアーにも慣れたみたいね。…くすくす…っ……そろそろ自分の立場が納得できたのかしら? ……生きたまま呑み込まれ、消化されるのを待つ餌の身分。……どんな気分かしらね、少し私も想像してみることにするわ…。」
カレンが笑い声を漏らす。耳の奥にこびりつくようなねっとりとした響きの中に、私がいくらか落ち着きを取り戻したことに対する微かな失望を感じ取ることができた。
餌の立場…そんなものが納得できるはずがない。観念した訳でも何でもない。
落ち着いたのは単純に、咀嚼や嚥下や、異常な状況によるショック状態から立ち直っただけだ。
すでに私が異常な事態を体験してからかなりの時間が経過している。
だが、落ち着いたところで事態そのものが改善するわけではない。
カレンの言葉通りなら、私は意識を失っている間に牛の消化器官のさらに奥までたどり着いてしまっているのだ。
意識を失い、眠ることで気分は落ち着いたが、逆に状況は逃げ場のない一本道のさらに奥底へと進んでしまっているのだった。
この状況を打破するための解決策がないか……。
幾分冷静さを取り戻した思考をどれだけ働かせても、その答えは出てきそうもなかった……。
「ずいぶん難しい顔をしているのね? 何か考え事でもしていたのかしら。……それよりも、見てみて。とても面白いことが起こり始めてるわ…」
私の面白くもない表情を見るのにも飽きてきたのだろう。
カレンが何か、カメラで見つけたものを示唆するように声をかけてきた。
何を見たというのだろうか。
見よう……と意識して視野を巡らせると、白く血色の引いた自らの手先が見えた。
意識を失っている間も、私の手はこのカプセルの取っ手を握りつづけていたらしい。無意識に力を込め続けていた手から不要な力を抜くと、掌に血液が流れ込みびりびりとしびれる感触が走った。
そのまま、周囲に視線を巡らせる。
周りに溜まっている消化物はかなり発酵が進んでいるらしく、暗い黄土色めいた土色に変色しぼこぼこと盛んに気泡を浮かべている。
蠕動は第一胃よりも緩やかで、湖面に波らしい波は感じない。
私の半身が沈み込んでいる消化物の粥はかなりなめらかなペースト状になっている。これが、元は草や紙のような固い物だ、とはにわかに信じがたかった。
普通、植物細胞を作るセルロースは胃では消化できない。
食物繊維と言う言葉がある。消化できないから固形のまま体内を通り抜ける。それが腸を綺麗にするのだ。
だが、粥のような湖水には繊維らしきものなど見あたらない。
一緒に呑み込まれたはずの、私が貼り付けられていた書類も跡形ない。
感心すべき状況ではないが、これは確かに貴重な体験になるのかもしれない……。
ふと、二の腕にむずかゆさを感じ、視線を腕へと落とした。
見れば丈夫なはずのスーツの腕の部分が破れてしまっていた。墨色のスーツの間に、白い素肌が露出してしまっている。
いつの間に破れたのだろう。むき出しになった直肌は、消化物の粥に浸っていたため心なしかふやけ、赤く上気した色合いを映し出している。
急に不安が押し寄せる。
スーツの他の部分を急いで確かめる。
腕だけではなかった。
耐久性に優れるはずのスーツが、あちこちで破れ穴を開けている。
まるで、安物のストッキングを穿いて藪を突っ切った後のような有様だ。
信じられない出来事だ。
肌がかゆくなる程度の化学物質でスーツが破られるはずがない。
肩に開いていた、大きな穴を塞ごうと両手で穴の縁を引っぱる。
しかしスーツを引っぱることはできなかった。
まるで、濡らしたトイレットペーパーを引っぱっているような感じだ。
ぶよぶよになったスーツが、指先に捕まるのを嫌うようにつまんだ部分から崩れ、ぞろりと腕を滑って崩れ落ちた。
「……これは、私にも予想できなかったすばらしい成果よ。…わかる? 細菌と酵素による分解の働き…そのナチュラル・メカニズムが、今、最先端の科学を集結したスーツのテクノロジーを凌駕したのよ! 信じられない。強靱な特殊素材さえお粥みたいにどろどろになってる……ああ…素晴らしいわ! 芸術的な瞬間に立ち会うことができたわ!!」
カレンの狂的な叫び声がけたたましく鳴った。
スーツが……。
分解されている…?!
急激に、胸が苦しくなる。強烈な吐き気が襲ってきた。
私は、牛の消化物の泥沼の中へ吐いた。
一度吐いてしまうと、それが止まらなくなった。
カプセルにとりついたまま、下を向き、げえげえと胃の内容物を吐き散らしつづけた。
吐いたものは泥沼の水面へ吸い込まれあっという間に見えなくなる。
見えなくなると言うより、湖面そのものとの区別が付かなくなるのだ。
胃が空っぽになっても吐き気は止まらない。
胃液を吐いた。何度も。
喉が焼けてしまい、ひどく痛んだが、鳩尾の奥の痛みはそれ以上だった。
「……スーツは発酵作用によって分解されるけれど人体はまだ溶かされないのね…興味深いメカニズムだわ…素敵。素敵、素敵……素敵っ。ああ、ああ……もう……あは、ふ…………あははははは……!」
カレンの狂ったような笑い声が胃壁にぶつかり木霊する。
人体は溶かされない……。
嘔吐の苦痛で朦朧とした意識で一節だけを復唱し続けた。
溶かされない…溶かされない…溶かされない…。
スーツが剥がれてむき出しになった肌が、消化物と触れ合い全身がぴりぴりとした痛痒感に包まれる
今にも身体が溶け崩れてしまいそうだ。
そうしている間にも確実に溶け、失われていくスーツの防御…。
頭が恐怖と嫌悪でいっぱいになる。
うわごとのように呟き続けた。溶かされない、と。
それを信じるだけの余裕はもう、なかった。
急に、静かだった湖面に流れが生じた。
カプセルが引っぱられ、手の力を完全に緩めていた私は湖面へどぶり、と投げ出された。
どろどろの粘流が身体を攫い、私を押し流す。
つぶやきも中断させられた。
カプセルからもぎ離された私は、最初に呑み込まれた時と同じように、木の葉のように翻弄されながら消化物の粘流と一緒に押し流される。
目を閉じることもできなかった。
開ききった瞳にどろどろの粥と、蜂の巣状の肉壁とがちらちらと照らし出される。
次の瞬間、私の身体は狭い通路へ一気に押し流された。
身体を分厚い肉の塊が挟み込んでいる。
まるで巨大な舌でサンドイッチにされているような感じだ。
その肉塊が私を挟んだまま蠕動し、蠢いて、私の全身を擦り上げる。
こすりつけられるたびに、肉の表面に並んだ無数の突起がむき出しの乳房や腿を這い回り刺激する。
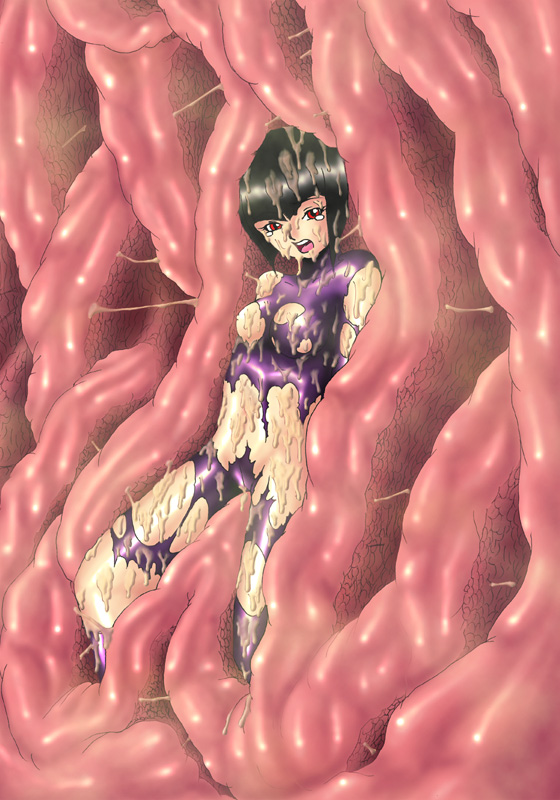
もう、手も、足も、動かすだけの体力は残っていない。
なすがまま、されるがままに肉壁に翻弄されるだけだ。
カレンは、ここを第三胃だと言っていた。ひだ状の肉壁の隙間で、食物はすり潰されるのだと。
スーツが溶け去り、剥き出しの乳房の上をざらざらの突起が執拗に往復する。
そのこまかな突起が乳首に粘液を塗りつけるたびに、背筋に甘い痺れが走り始めていた。
もう、何も考えてはいない。
痺れは甘く、脳は麻痺し…疼きは腰の付け根へと溜まり奥へと染みこんでゆく…。
股間にとろりと、蜜が滲むのを感じた。
じっとりとした粘液…身体が奥から溶けだしたかのようで、さらに全身から力が抜けていく。
閉じていた脚が弛緩し、開いた。
ずる、と身体が滑り落ち、脚の間に新たな丘陵が挟まってくる。
くまなく突起に覆われた襞が脚の内側を撫で、粘液を塗りつけてくる。
上気した皮膚は薄く、柔らかく、その裏側にある神経を直に弄られているような…ぞくぞくとする刺激が脊髄を駆け抜ける。
襞の先端が付け根に届いた。
とろとろに濡れた秘唇を割って、ぬるぬると粘液に濡れたぶつぶつの突起が身体の内側を撫でる。
力が入らぬはずの腰が跳ねた。
何か、うわごとのように喘ぎを漏らしてしまう。
すべてが遠いところで起こっているような感覚の中…。
周囲の襞の動きが徐々に強くなっていた。
この襞だらけの器官のずいぶん深い場所まで運び込まれていたようだった。
足先が、熱い肉の塊につっこんだような感触があった。
……また、奥へ運ばれるのだ。
全身がぬるぬるにふやけているからひっかかることはなかった。
ずる…っ、と襞の合間を滑り落ち、全身を撫でられると、たまらなく甘い痺れが全身を駆け抜けた。
断続的に走る軽い絶頂感の中、膝が、腿が肉に呑まれていくのを感じる。
熱湯のような熱い刺激が腰から下を完全に包み込む。
周囲の肉襞が一斉に収縮し、上半身を覆った。
襞に押されるようにして、乳房のすぐ下までが肉の沼へ沈み込む。
乳房が入口を抜ければ…あとは早かった。
あっという間に頬や額が熱い、濡れた肉に受け止められる。
最後にそろえた両腕が熱の中に包み込まれた。
ぬるぬると、熱い肉の中を運ばれているのが分かった。
カレンの説明でこの後どこへ行くのかは分かっていた。
第四胃。
本来の胃と同じ、強酸の消化液による消化を行うところだ。
……私はまもなく溶かされる。
…いや、身体の奥はもう、とろけ切っている…。
とぎれる事なく続く絶頂感がもたらす脱力と快感との中で。
母の胎内に居るような、心地よさ…。
膝を抱え、胎児の姿勢で。
「…完全に溶けてしまったみたいね。」
カレン・ウィンターマンは雄大に壁面をうねらせ蠕動する第四胃の映像から瞳をはずすと、やや残念そうな声を上げ、軽く親指の爪を噛んだ。
めくるめく映像は彼女が経験した中でも最高の、エクスタシーをもたらす映像だった。
5cmに縮められた侵入者は、その身体をいっぱいに使った演技で彼女を楽しませ続けてくれたのだった。
もっと楽しみたかった。
だが、ショーの主役は濃密に分泌される消化液で溶けてしまい、もはや骨の断片すら発見できなかった。
「……次のショーを考えなければ…いけないのね」
カレンは、ため息をついてデスクを蹴り、椅子から立ち上がる。
すぐに、その表情が笑みへと代わった。
「ああ…次はどんなショーを催しましょう。…巨大な魔物に挑む伝説の英雄を再現するのがいいかしら、それとも古の神に捧げられる悲運の乙女? キャンディでコーティングした子を口の中でゆっくり溶かすのもいいわね…。それに……あとは……くす…っ。……ふふ…………あはは……あはははははは……!」
唇に浮かんだわずかな笑みは、忍び笑いになり、それは溢れる哄笑へと変じる。
カレンの脳裏には、新しいショーの脚本がとめどなく溢れ出してきていた。
これから忙しくなる。まず、ショーの舞台を準備しなくてはならない。
そして、新しいアクトレスも……。