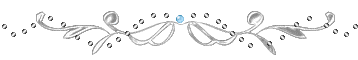
風邪を引いた日

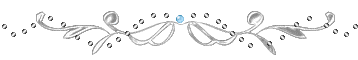
風邪を引いた日

目を覚ますと、喉が痛くて少し熱っぽいような気がした。 …ヤバい。風邪引いたかな。
ゆうべ、何か寒気がするなあなんて思ってたんだ。でもまあ、幸い仕事は昼間のラジオの中継がちょこっとだけだし、なんとか乗り切れるだろう。一応、熱でも計っておこうか…。
身支度を整えながら、軽い気持ちで体温計を口にくわえた。それが間違いだった。
「……………。」
ピピッ、と鳴ったので口から出して見たら。あまりの数値に目を疑った。
「さ…三十八度ぉ?!」
思わず素っ頓狂な声を上げてしまった。そんなバカな。壊れてんじゃねーか?これ。
「と…とりあえずもう出掛けないと…」
三十八度などという数値を見てしまったせいか、途端に足元がふらついてきたような気がする。薬…は、腹に何か入れてからじゃないと飲めないから…途中でコンビニ寄って、何か適当に買うとして…。薬の買い置き、あった筈だよな?薬、薬…。何処にしまったっけ?何せ俺の部屋は人が住んでるとは思えない程の散らかりようで、買っといた筈なのになかなか探し出せない。そうこうしてるうちに、裕次郎が擦り寄ってきて。
「にゃーん…」
ああ、ごめん。お前の餌、忘れてた。薬を探すのを中断して、猫缶を開けてやる。美味そうにガツガツ食ってるの見てると、何だか幸せになる。
「美味い?裕次郎」
しゃがみこんで愛猫が餌食ってるところを暫く見つめてて、はっとする。
「ああっ!やばいっ、遅刻する!」
…結局薬も探し出せず、コンビニで飯も買えないまま、局入りするはめになってしまったのであった。頭がボーッとしてきていたので、車の運転は諦めてタクシーで局に向かった。
![]()
その日の中継は、何を喋ったか覚えていない。中継車で待機している間にも、どんどん具合が悪くなってきてて。何とか上手く乗り切らねばと、そればかりが頭にあって。多少とんちんかんなことを言ったかもしれないけど、そこはスタジオの方でフォローしてくれただろう。
仕事が終わると、俺は早々に自宅に戻った。熱くて、喉が痛くて、足元がおぼつかない。帰宅途中に飯や薬を買う余裕も無く、服を脱ぎ捨ててベッドにもぐり込んだ。とにかく早く横になりたくて。横になってふーっと息をつく。明日までに熱だけでも下がればいいな、なんてことを考えながら、眠りについた。
![]()
どれくらい眠っていただろう。目を覚ますと、外は真っ暗だった。もそもそと起き上がり、ベッド脇のスタンドをぱち、とつけた。時計は七時半を回っていた。
「七時半…三時間は寝たかぁ……」
身体のだるさは少しはいい感じ。明日のことを考えれば、何か食って薬を飲んだ方がいいのだろうが、仕度するのも億劫。薬を発掘する気力も無ければ、外に買いに行く気力も全く無い。まあ、寝てりゃ治るだろう…。そう思ってまた眠りにつこうとした、その時。枕の脇に置いてあった携帯が鳴った。出るのも億劫だったけど、仕事絡みかもしれないしと思い、仕方なく手に取った。
「…あ、顕ちゃんだ…」
そういえば…何か忘れてるような気がするぞ。ピ、とボタンを押して、電話に出た。
「もしもし…」
思っていたより酷い声で、自分自身びっくりしてしまった。
「た…琢ちゃん?何だよその声」
顕ちゃんも驚いてる。そりゃそうだよな、凄い嗄れ声だもの。
「…風邪引いて、今朝から具合悪くて…」
「寝てたの?ごめん、悪いことしちゃったね」
本当に申し訳無さそうな、顕ちゃんの声。
「んーん、それよりどしたの?」
顕ちゃんが電話してくるなんて珍しいことだし。俺の問いに、顕ちゃんは言いづらそうに言った。
「いや…、今日さ、待ち合わせの約束してたでしょ。七時に。遅いから、どうしたかなって思ってさ」
………そうだった。顕ちゃんが夜空いてるっていうから、久々に一緒に飯でも食って、映画でも観ようかなんて言ってたんだっけ。この体調のせいで、すっかり忘れてた。
「ごめん顕ちゃん…忘れてた」
「いいよそんな、謝らなくても。それより飯とか薬は?ちゃんと何か腹に入れてる?」
…そういえば、朝から何も食べてない…薬も。
「いやあ…めんどくさくて、ただ寝てた…」
言ったあと、電話の向こうでは何やら考え込んでる様子。
「…迷惑じゃなければ、今からそっち行きたいんだけど。いいかな」
「うん…でも、俺何も出来ないよ?」
俺の返答に、電話の向こうの顕ちゃんが溜息をつく。
「琢ちゃんが何も出来ないから、俺が行くんでしょ。少しは歩ける?玄関の鍵開けられるかな」
「うん、それくらいは出来る…」
二、三十分で行くと言って、顕ちゃんは電話を切った。出来る、とは言ったものの、ちゃんと歩けるかさえ定かでない。試しにベッドから降りて、立ち上がってみた。ちょっとフラフラする。玄関に向かって歩いてみると、やっぱりまだ足元がおぼつかない。
「……あー…やばいなあ……」
何とか玄関に辿り着き鍵を開けたあと、立っていられなくてその場に座り込んでしまった。熱くてボーッとしてるから、ひんやりした空気が肌に心地いい。壁にもたれて一息ついた。
ピンポーン…
チャイムが鳴った。顕ちゃん、早かったなあ。無茶な運転してきたんじゃないだろうな。
「顕ちゃんでしょ?開いてるよー」
立ち上がるのが面倒で、俺は座り込んだまま。ガチャ、とドアが開いて、顕ちゃんが顔を出した。
「お邪魔しまーす…って、琢ちゃん!!何してんのそんなカッコで!!」
…そう言えば、着替えるのも面倒で脱ぎっぱなしだったっけ。Tシャツに、下はトランクスのまま。
「着替え億劫だったし、熱いし…。気持ちいいよー」
熱のせいか、ハイになってるみたいだ。ヘラヘラ笑ってしまう。
「ダメだよ、ちゃんと寝てないと。立てる?」
顕ちゃんが手を差し出した。俺はその手を掴んで、よいしょ、と立ち上がった。顕ちゃんの手は、ひんやり冷たくて気持ちいい。
「…あー、外、寒いんだあ…」
「うん、夕方からかなり冷えてきたよ。…あ、ストーブ点けるね」
「うん」
顕ちゃんに手を借りて、俺はまたベッドに潜り込んだ。
「ああ、凄い高いじゃない。計ってる?」
俺のおでこに手をあてて、顕ちゃんが言った。
「仕事出掛ける前は三十八度だったけど…帰ってからは計ってない…」
「一応計っとこうか。はい」
体温計を口に入れてくれて、顕ちゃんはキッチンの方へ行った。何やら、カチャカチャと音がする。………裕次郎がいるから、独りぼっちって訳では無かったけど。顕ちゃんが来てくれて初めて、心細くて寂しかったんだと気付かされた。所構わずベタベタしてくるのはウザいと思うこともあるけど、こんな風に世話焼かれるのは心地いい。
「今、レトルトだけどお粥用意してるから。薬も買ってきたからね」
アイスノンを手に、顕ちゃんが顔を出した。勝手知ったるなんとやらで、タンスからタオルを出してそれをくるんだ。体温計、と言われて口を開ける。
「…上がってるよ…三十八度四分。熱いって言ったよね」
「ん…、寒気はないよ」
手に持っていたアイスノンを頭の下に入れてくれ、おでこには冷えぴたシート。
「…こんなに気がきく顕ちゃん、顕ちゃんじゃないみたいだ…」
「…そういうこと言う元気はある訳だ」
顕ちゃんは憮然とした顔をして、キッチンの方へ行った。レトルトとはいえお粥と野菜スープを用意してくれ、自分で食べれるっつーのに、わざわざ食べさせてくれた。薬も飲ませてくれて、キッチンからは後片付けの音が聞こえる。―――――――薬、効いてきたかなあ。それとも、安心したせいかな。眠くなってきた。
「琢ちゃん、じゃあ僕そろそろ帰るね。冷蔵庫にジュースとか果物とか入ってるから、ちゃんと水分補給するんだよ」
眠いせいか、顕ちゃんの声が遠くから聞こえる気がする。帰ると聞いて、途端に寂しくなる。
「…琢ちゃん?」
俺は無意識に、顕ちゃんのシャツの袖口を引っ張っていた。
「…なんだぁ…、もう帰っちゃうの…?」
「えっ…いや、だって…」
何でか、しどろもどろな顕ちゃん。
「…あー、朝早いの?明日…」
「いや、dondonだけ」
…何だよ。なら、まだ居てくれたっていいじゃないか。顕ちゃんのケチ。………いや、こんなの逆ギレだ。約束すっぽかしたのに心配して来てくれて、飯だの薬だのと世話焼いてくれたのに。
「琢ちゃん?」
黙り込んだ俺を、顕ちゃんが困ったように見てる。
「…ごめん、我が儘言って…。いろいろありがとね。今度埋め合わせ、するからね」
「…………」
「顕ちゃん?」
今度は顕ちゃんが黙ってしまった。じっと俺の顔、見てる。
「どしたの?」
「…いや、捨てられた子犬みたいな顔するから…」
は?何だそれ?その表現。―――――と、顕ちゃんが続けて言い始めた。
「その…、琢ちゃんがね、……目とか潤んでてねほっぺも上気してて…うっすら汗なんかかいちゃってるのが、ね…。…色っぽくて」
…何言ってんの?顕ちゃん。
「…色っぽくて可愛いから、僕の理性がね…保てる自信が無くて」
…………はあ?なんだよ、つまり。俺に欲情したから帰るってこと?
「病人相手に、そんなこと考えちゃってる自分が嫌でね…」
…………ぷっ。思わず吹き出してしまった。顕ちゃんは訝しげに俺を見てる。可愛いのは、顕ちゃんの方じゃないか。ひとしきり笑ったせいで、頭がクラクラしてしまった。
「そんなに可笑しいかな…」
「可笑しいっていうか、可愛いわ、顕ちゃん」
ほんとに、この男は。くそ真面目で、優しくて。――――――熱のせいで思考が大胆になっているのか、俺は思わず言ってしまった。
「…しようか、顕ちゃん…」
顕ちゃんは驚いて俺を見つめた後、そっと俺の頬に触れ、唇が降りて――――きたところで、俺ははっと気付いた。
「ごめん、やっぱりダメ!!」
唇が触れ合う寸前、思いっきり手のひらで顕ちゃんの顔を、びたん!と押さえつけてしまった。
「…琢ちゃん…」
なんで?って疑問と、ちよっぴり怒りも混じってるかのような声。だって。
「い、いや、えっちは構わないけど、キスはダメ!唇はダメ!!うつるから!!」
―――――シーン……ほんの少しの、間。今度は顕ちゃんが吹き出した。だって、帯でレギュラー持ってるじゃないか。仕事は外だし、風邪なんか引いちゃったら、俺より大変じゃないか。だから。
「僕も抜けてるとこあるけどさあ、琢ちゃんも…天然だよなあ」
…反論できない。押さえつけてしまった顕ちゃんの顔が、ちょっぴり赤くなってる。
「ご、ごめん…」
「いや、僕の方こそごめん。真に受けちゃって」
…それは誘ったりした俺の方が悪いんじゃないかる何で謝ってくれちゃうんだよ。顕ちゃんは、優しく笑って言った。
「やっぱり帰るよ。琢ちゃん、ゆっくり眠らないと。早く治ってくれないと、手が出せないからね」
…返答に困る。帰る間際、顕ちゃんは頬にキスをして、悪戯っぽい笑みを浮かべて言った。
「今日の貸しは大きいからね、琢ちゃん。元気になったら、たっぷり返して貰うよ。……体で、ね」
![]()
後日、風邪が完治した俺は、本当にたっぷりと体で借りを返すハメになり………大いに泣かされたのであった。前言撤回、優しいなんて嘘だ。そう毒づいても、結局この男から逃げ出せないのは分かってるけど。