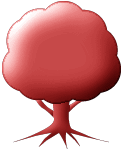
懠偺僄儞僨傿儞僌傊
僴儘僂傿儞偼戝憶偓丂乣僐儘僯僗僩晽枴Ver乣丂丂By丂杛寧
偙偆側偭偨傜偲偙偲傫晠傟偰傗傠偆偲巚偭偰彂偒傑偟偨乮徫乯
偁傫傑傝偲尵偊偽偁傫傑傝側丄柍棟傗傝偹偠傑偘僐儘僯僗僩晽枴僆僠偱偡偺偱丄
儂儞僩丄偍姪傔偱偒傑偣傫偱偡丅 偲傎傎丅
擇恖偵傆偭偲偽偝傟偨Mulder偼丄愜妏擼恔峁偐傜暅妶偟偨偺偵傑偨搢傟偰偄傞丅
摉慠偩丅
垽偺椡偱擱偊傞Frohike偲僋僗儕偺椡偱夡傟偨Skinner偑憡庤偠傖傂偲偨傑傝傕側偄丅
Langly 乽傑偁丄帺嬈帺摼偩傠乿
Byers 乽偁偁慡偔偩乨乨偙偭偪偼戝嵭擄偩傛乿
Langly偑尐傪鈵傔傞偲丄Byers偼搳偘弌偝傟偨彴偐傜僘儖僘儖恎傪婲偙偟側偑傜欔偄偨丅
偦偺帪乨乨
Scully 乽乨乨乨偭偁偭乨乨乨乿
彫偝側欙偒惡偲嫟偵Scully偑儀僢僪偵傌偨偭偲嵗傝崬傫偩丅
ALL 乽Scully両丠乿
偦偺応偺慡堳偑Scully傪怳傝曉偭偨丅
偲偭偝偵丄Scully偼戝忎晇丄偲偄偆傛偆偵塃庤傪忋偘偨丅
Scully 乽偄偊丄壗偱傕側偄傢乨乨乨婥偵偟側偄偱乿
偦傟偩偗尵偆偲丄尐傪戝偒偔忋壓偝偣側偑傜丄怺屇媧丅
乮乨乨乨偙偺姶妎偼乨乨乨傑偝偐丄偝偭偒偺栻乨乨乨乯
Frohike 乽Scully丄戝忎晇偐偄丠乿
Scully 乽偊丄偊偊丄懡暘偪傚偭偲恎懱偑椻偊偨偺傛乿
Skinner 乽壗張偐埆偄偺偐丠乿
Scully 乽偄偊丄懡暘晽幾偺弶婜徢忬偱偡丄Sir乿
杍傪峠挭偝偣側偑傜丄偦傟偱傕帺暘偺偐傜偩偺曄挷傪屽傜傟傑偄偲
Scully偼偲傝偁偊偢偵偭偙傝旝徫傫偱傒偨丅
怱攝偦偆偵丄偙偙偧偲偽偐傝偵偵偠傝婑傞Frohike偲Skinner丅
Skinner 乽偩偑丄壗偩偐擬偱傕偁傞傛偆偩偧乨乨乿
尵偄側偑傜Skinner偑Scully偺妟偵庤傪摉偰傛偆偲偟偨弖娫丄Scully偑堦弖慡恎傪
傃偔傝偭偲嫮挘傜偣偨丅
Scully 乽偼偭乨乨乨偁偁偭!!乿
乗劅乗乗劅乗!!!???
偁傑傝偵傕墣偺偁傞歜偓偵偦偺応偺慡堳偑搥傝偮偒丄栚傪娵偔偡傞丅
乗劅乗偟傑偭偨乨乨乨
Scully偼帺暘偺惡偵帺暘偱嬃偒丄岥傪庤偱嵡偄偩丅
乮傑偢偄傢乨乨乨偁偺栻丄岠偒偑憗夁偓傞乨乨乨両乯
Skinner 乽Scully乨乨孨偼偦偺乨乨傗偭傁傝儅僢僠儑側乨乨乿
崱峏側偑傜丄傕偠傕偠偟側偑傜恞偹傞Skinner丅
Scully 乽乨乨乨乨Sir丠乿
偳偆傗傜Skinner丄傑偩乽儅僢僠儑側僆僇儅偵乣乿偺審傪妎偊偰偄偨傜偟偄丅
Scully 乽偳丄偳偆偐偟傑偟偨偐丠乿
Skinner 乽乨乨乨乨偄傗丄偦偺乨乨乨壗偱傕側偄乨乨乨乿
乗劅乗偳偆傗傜僴僘儗偩偭偨傜偟偄丅
堦弖乽丠乿偲偄偆昞忣傪尒偣偨Scully偩偭偨偑丄姼偊偰偦偺審偵偼怗傟偢丄
傂偲傑偢偵偭偙傝旝徫傫偩丅
乮偲偵偐偔丄斵傜傪傑偢偼婣傜偣側偄偲乨乨乨乯
Scully 乽偦傟傛傝傕Sir丄偦偺奿岲偺傑傑偱偼摴傪曕偄偰婣傞栿偵偼偄偒傑偣傫傢偹丠乿
Skinner
乽乨乨乨偦傟傕偦偆偩側乨乨乨乿
乗劅乗揤壓偺FBI暃挿姱偑摴抂偱寈姱偺怑柋幙栤傪庴偗傞偲偄偆偺傕尒暔偐傕偟傟側偄偑丅
Scully 乽Frohike丄Langry丄Byers乨乨乨埆偄傫偩偗偳丄Sir傪斵偺壠傑偱憲偭偰傕傜偊側偄偐偟傜丅
幵偼巹偺傪巊偭偰偔傟偰峔傢側偄傢丅偦偺傑傑忔偭偰婣偭偰傕傜偭偰傕乿
Langry 乽偁偁丄偦傟側傜巊傢偣偰傕傜偆傛乿
Scully 乽埆偄傢偹乿
Byers 乽峔傢傫偝丅偦傟傛傝乿
晹壆偺嬿偵揮偑偭偰偄傞Mulder偑彫偝偔偆傔偒側偑傜恎傪婲偙偟偐偗偰偄傞丅
Frohike偼偦傟傪妠偱偟傖偔偭偰嵎偟偨丅
Frohike 乽偁偄偮傕楢傟偰婣傞傛丅偙傟埲忋孨偺懁偵抲偄偰偍偔偲婋尟偩乿
Scully
乽斵偼巹偑壗偲偐偡傞傢丅傑偩擼恔峁婲偙偟偨偽偭偐傝偱條巕傕尒側偒傖偄偗側偄偟乿
Frohike 乽偱傕丄儎僣偼孨偵壗傪偡傞偐傢偐傜側偄偧乿
乮偍偄偍偄丄恖傪壗偐偺僿儞僞僀偲姩堘偄偟偰側偄偐丠乯
尵偄偐偗偰岥傪偮傓偖Mulder丅
乗劅乗乗妋偐偵偦偆偐傕偟傟側偄乨乨乨乨
Scully 乽戝忎晇傛丅偄偞偲側傟偽堦敪寕偪崬傫偱偁偘傞偔傜偄偺帠偼偱偒傞偟乿
Scully偼儀僢僪僒僀僪偺堷偒弌偟偺拞偐傜偍傕傓傠偵対廵傪庢傝忋偘偰偪傜偮偐偣偨丅
乗劅乗乗偁側偑偪娫堘偭偰側偄偐傜晐偄丅
乮偦傟傛傝丄偍婅偄偩偐傜憗偔乨乨乨乯
Scully偼丄師戞偵傂偳偔側傞摦梙偲恎懱偺恔偊偲傪偄偮傕偺壖柺偺壓偵傂偨塀偟偨丅
乮壗偲偐偟偰乨乨乨夝撆嵻傪乨乨乨乯
Byers 乽偦傟偠傖丄幐楃偡傞傛丅崱擔偼妝偟偐偭偨傛乿
Scully 乽偄傠偄傠屼柪榝傪偐偗偰怽偟栿側偄傢乿
Langly 乽傑偨傗傞側傜崱搙偼栻暔偼敳偒偵偟偰梸偟偄側乿
Scully
乽偊偊丄傑偭偨偔両乨乨乨偍旀傟偝傑偱偟偨傢丄Sir乿
Skinner 乽婥傪偮偗傞傫偩偧丄偄傠偄傠偲乿
Frohike
乽摿偵儎僣偵偼婥傪偮偗偰両乿
係恖岥乆偵偄傠偄傠尵偄側偑傜僪傾傪偔偖偭偰偄偔丅
Scully偼慡堳傪尒偊側偔側傞傑偱尒憲傝丄屻傠庤偵僪傾傪暵偠丄惷偐偵尞傪妡偗傞丅
僥乕儖儔儞僾偑妏傪嬋偑偭偰峴偔乨乨乨
Scully 乽Mulder丄戝忎晇偹丠乿
Scully偺惡偑嬤偯偄偰偔傞丅
Mulder偼墸傜傟偨杍傪嶤傝側偑傜恎懱傪暻偵梐偗傞條偵偟偰婲偒忋偑偭偨丅
Mulder 乽偁偁丄懡暘堎忢側偟偩乿
Scully 乽偦偆傒偨偄偹乨乨乿
Scully偼偡偭偲Mulder偵岦偐偄崌偆條偵偟偰偟傖偑傒偙傓丅
Mulder偺妠偵寉偔塃庤傪偁偰偑偄側偑傜嵍塃偺杍傪尒斾傋傞Scully丅
乗劅乗偦偺敀偄巜愭偑嵶偐偔恔偊偰偄傞偺偼姦偝偺偣偄偩傠偆偐丠
Scully 乽摢偼丠柇側摢捝偲偐偼柍偄傢偹丠乿
Mulder 乽偲傝偁偊偢丅怱攝偟偰偔傟偨丠乿
Scully 乽摉偨傝慜偱偟傚偆丠僷乕僩僫乕側傫偩偐傜乿
傎傫偺傝庨偵愼傑偭偨杍丅寉偔抏傓屇媧丅
昞忣偼偄偮傕捠傝僋乕儖側偺偵丄壗屘偐彮偟暁栚偑偪偵尒偊傞丅
崾栄偑偦偺摰傪塀偟偰偟傑偭偰丄昞忣偑撉傔側偄丅
乗劅乗壗偐傪旔偗偰偄傞條側乨乨乨乨
偟偐偟丄偦傫側帠偑偳偆偱傕椙偔側傞偔傜偄丄Scully偺揻懅偼Mulder偺帹傪
娒偔偔偡偖偭偰棧偝側偐偭偨丅
Mulder 乽Scully丄傕偟偐偟偰丄偝偭偒偺栻偑岠偄偰偒偰側偄偐丠乿
寉偄峥濖傪姶偠側偑傜傑偠傑偠偲Scully偺摰傪尒偮傔傞Mulder丅
Scully偼旣傪彫偝偔忋偘偰尐傪鈵傔傞偲丄岥偺抂偩偗偱旝徫傫偩丅
Scully 乽岠偄偰偄傞傒偨偄傛乨乨偳偆傕婥暘偑埆偄傢丅揻偒婥偑偡傞偺丅
Mulder丄偁側偨夝撆嵻帩偭偰傞偺丠乿
Mulder 乽乨乨偄傗丄柍偄傫偩乨乨懡暘悢帪娫偱岠壥偼徚偊傞偲巚偆乿
Scully 乽乨乨偦偆乿
傗傗偦偭偗側偔傕暦偙偊傞偦偺曉摎丅
偩偑丄柧傜偐偵Scully偺帇慄偼Mulder傪偦偺応偵搥傝偮偐偣偰偄傞丅
攚嬝偑僝僋僝僋偡傞傎偳偮傗傗偐側昞忣丅
傑傞偱杔偺恀堄傪抦偭偰偄傞傛偆側乨乨乨
乗劅乗Scully丄孨偼壗傪婇傫偱乨乨乨乨丠
Mulder 乽偦偺乨乨恎懱偑擬偔側偭偨傝偟偰側偄偐丠偦偺栻偵偼沍栻偺惉暘偑偐側傝
擖偭偰偄傞偼偢側傫偩偗偳乿
Scully 乽偄偄偊丄偦傟偼柍偄傢乨乨乨偦傫側偲偙傠偩傠偆偲偼巚偭偨偗偳丅
僷乕僥傿乕偺梋嫽偵偟偰傕丄彮乆搙偑夁偓傞傢偹乿
Scully偼曫傟偰丄傆偆偭偲棴懅傪偮偄偨丅
偦傟偵崌傢偣偰丄帹偵偐偐傝偒傜偢偵棊偪偰偒偨婔朳偐偺嬥偺敮偑寧柧偐傝偵梙傟傞丅
乗劅乗傠偔側偙偲傪峫偊側偄傢偹丄偲偱傕巚偭偰偄傞偺偩傠偆偐丠
乨乨乨偦傟偲傕乨乨乨
Scully 乽偦傟傛傝乨乨乨偦偺栻傪搉偟偰傕傜偊側偄偐偟傜丠乿
Mulder 乽乨乨乨壗偐偵巊偆偺偐丠乿
Scully 乽夝撆嵻傪壗偲偐偡傞偵寛傑偭偰傞偱偟傚偆丠乿
Mulder 乽偱傕丄偁偲悢帪娫変枬偡傟偽乨乨乨乿
Scully 乽偦偺悢帪娫偑懸偰側偄偔傜偄丄婥暘偑埆偄偺傛丅惉暘偑暘偐傟偽
壗偲偐側傞偐傕偟傟側偄傢乿
Mulder 乽偱傕乨乨乿
Scully 乽偄偄偐傜丄戄偟側偝偄両乿
傗傗嫮偄岥挷偱尵偄曻偮偲丄Scully偼Mulder偺億働僢僩偐傜彫時傪堷偭挘傝弌偟偨丅
偦偺傑傑壗傕尵傢偢偵時偺奧傪庢傝丄堦婥偵岥偵娷傓丅
Mulder 乽Scully!?壗傪偭乨乨乨乿
巚傢偢惡偑忋偢傞丅
堦弖丄Scully偺栚嫋偵壗偐偑岝偭偨條側婥偑偟偨丅
乗劅乗壗乨乨乨乨!?
Scully偼栚傪尒奐偄偨傑傑偺Mulder偺旲傪嵡偓岥傪偙偠奐偗丄恖岺屇媧偺梫椞偱岥堏偟偵丄
偦偺塼懱傪Mulder偺拞偵棳偟崬傓丅
Mulder 乽!!!??乿
偄偭傁偄偵拲偑傟傞杺朄偺幋丅
嬯偟偘偵旣崻傪婑偣傞Scully偺妟偵偼丄傕偆庫偺娋偑晜偒忋偑傝巒傔偰偄偨丅
怬偺崌傢偣栚偐傜偙傏傟偨堦揌偑杍傪揱偄丄庱嬝傪偡傋偭偰嵔崪偺孍傒傑偱棊偪傞丅
塀旝偱娒傗偐側崄傝偑棫偪偺傏偭偰偔傞丅
岮偵媧偄崬傑傟傞塼懱偼丄椺偊條偺柍偄壏傕傝傪懷傃偰偄偨丅
乮Scully丄孨偼乨乨乨乨!?乯
傂偲岥乨乨乨傑偨傂偲岥丅
彫時偑姳忋偑偭偰偄偔丅
乗劅乗偙傟偼丄沍栻乨乨乨乨
Mulder偼栚傪暵偠傞偲丄偡傋偰傪枴傢偆條偵偦傟傪堸傒姳偟偨丅
擇攖栚傪拲偓廔偊偨Scully偺怬偑丄彫偝偔殤偒偐偗傞丅
Scully 乽偙傟偔傜偄懳摍偵偟側偄偲丄僼僃傾偠傖側偄傢乨乨乨乿
Mulder偺椉杍傪丄Scully偺椉偺庤偺傂傜偑嫴傒崬傓丅
栚偺慜丄傎傫偺侾侽噋傎偳偺丄揻懅偑怗傟傞嫍棧丅
擬偭傐偔弫傫偩暽偺摰偑Mulder偺愐悜偵揹寕傪憱傜偣傞丅
乗劅乗恎懱偺墱偐傜桸偒忋偑傞姶忣丅
Scully偼偦傟傪Mulder偺昞忣偺拞偵姶偠庢偭偨偺偐丄傆傢傝偲旝徫傒丄偦偭偲崾栄傪暁偣偨丅
偦偺偁傑傝偺墣傗偐偝乗劅乗乗
梿慁奒抜傪揮偑傝懧偪偰偄偔傛偆側丄寖偟偄峥濖偑偟偨丅
Scully 乽愑擟傪庢偭偰乨乨乨乨偡傋偰偼婱曽偺偣偄偱偟傚偆丠乿
揻懅崿偠傝偺丄偪傚偭偲偐偡傟偨惡丅
崱偵傕媰偒弌偟偦偆側婄偺傑傑丄Scully偼Mulder偺旼偵攏忔傝偵側傝丄忋拝偵庤傪妡偗傞丅
Scully 乽柧擔栚偑妎傔偨傜丄柌偩偭偨偲巚偭偰朰傟偰乨乨乨乿
Mulder 乽乨乨乨乨傕偟朰傟傜傟傞側傜丄偹乿
僔儍僣偺拞偵妸傝崬傓彮偟椻偊偨巜愭傪姶偠側偑傜丄Mulder偼Scully偺嵶偄尐傪書偒掲傔丄
偦偺攚拞偺僼傽僗僫乕傪備偭偔傝偲堷偒壓傠偡丅
彮偟偢偮丄恎懱偑栻偲杮擻偵巟攝偝傟偰偄偔丅
乗劅乗乗劅朰傟傜傟傞栿偑側偄偩傠偆丠
偙傫側偵傕嫮偔朷傫偩傕偺傪庤偵擖傟傜傟傞弖娫傪丅
傎偐偵偼壗傕梫傜側偄偲尵偊傞丄偙偺弖娫傪丅
乽柍拑傪尵偆偺偼杔偺愱攧摿嫋偩偭偨敜側偺偵側乨乨乨乿
Scully偺敀偄尐偑傎偺偐側寧柧偐傝偵晜偐傃忋偑傞丅
Mulder偼嵟屻偵偦傟偩偗欔偔偲丄怺偄埫埮偺拞傊棟惈傪夝偒曻偭偨乨乨乨乨
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂佱FIN佲
乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣
佱巒枛彂佲
偼偆乨乨乨壗偠傖偙傝傖乮徫乯
傎偲傫偳巹暔壔偟偰偟傑偄傑偟偨乨乨僑儊儞僫僒僀丅偁偁幱偭偰偽偭偐傝丅
偁偨偟偺恖惗偦傫側傫偽偭偐偱偡傢丅偛傎偛傎丅
偙傫側傫偱偄偄傫偩傠偆偐乨乨乨
19991113丂杛寧丂乮晽幾偺昦彴偐傜乮徫乯僆僀僆僀丅乯
E-mail丂丗丂mutsuki5@anet.ne.jp
乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣乣