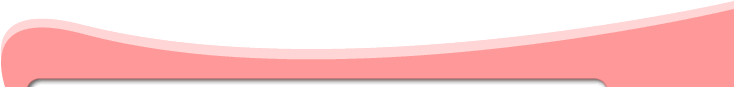|
「だんだん暗くなってきたね」
怜子さんが言った。「そろそろ帰らないと」
「……うん」
裸のオシリで床のマットに座ってるのが急に恥ずかしくなってきて、あたしは両膝を抱えて下を向いた。
「どうしよう、あたし……これじゃ帰れないよ……」
「大丈夫よ」
玲子さんが脱ぎ散らかしたあたしの服を拾い集めて言った。パンツはもちろん、スカートから靴下までちょっとスゴイことになってて、あたしはツ、と目をそらした。
「そんなの、もう着れないよ」
あたしは言った。
「大丈夫だって」
怜子さんはクスクス笑って、そばに腰を下ろすと胸に手をまわしてきた。抱き寄せられて、
「唇、いい?」
うなずく間もなく唇を吸われた。怜子さんの舌が中に入ってくる。
「あ……」
「今日は楽しかった」
「ん……」
また唇を吸われてあたしは鼻で息をした。酸っぱいようなオシッコの臭いが鼻をついて、あたしはまた不安になる。すこしオシリを浮かせると、床のマットにハート型のシミが出来ていた。
「大丈夫よ」
と、怜子さんは言うと、制服に向かって口の中で何かブツブツつぶやきだした。待つこと数秒――
「ホラ」
怜子さんがパンツの汚れた部分を広げて見せた。
「触ってみて」
触ってみると少し湿ってるくらいになっていた。さっきまで雫がポタポタ垂れていたのに、パンツはホカホカと暖かくてかすかに白い湯気がたっている。
「すごい……」
パンツを手で取って、それからコホコホと咳き込んだ。乾いたオシッコのニオイで鼻の奥がツンとする。
「オシッコくさい……さっきよりも酷くなってるよ」
「それは仕方ないよ。乾いただけでもいいと思わないと。ほら足上げて、パンツなしじゃ帰れないでしょ」
「う、うん」
怜子さんの肩に手を置いて、あたしは片足を上げた。パンツのシミをできるだけ見ないようにして足を通して、
「ニオイが……ばれちゃうよ。きっと」
「緋奈の臭いだなんて誰も思わないわよ、きっと」
怜子さんが言った。
「楽観的すぎるよ」
と言うと、怜子さんはフフと笑って、
「大丈夫よ。術をかけたんだから」
「ホントに?」
「嘘じゃないわ」
「ホントにホント?」
スカートのホックを止めてもらいながら、あたしはチラッとスカートの前を見た。ばっちりついた黄色いシミを確認する。
「ぜったいに分かんないから、ほら次は靴下。こっちの足出して」
「……ん」
「家まで着いてきてくれるの?」
ブラウスのボタンを留めてもらいながら、あたしは言った。
「もちろん。でも日が暮れるまでよ。日が暮れる前に帰らないと」
「ユウレイなのに? なんだか反対ね」
「私は陽に属する霊だから。夜は、それ専門の時間帯ね」
「……夜専門、って?」
「聞いたら、夜おトイレ行けなくなっちゃうぞ」
ツンと指で鼻をはじかれた。
「さ、帰ろうか。いそがないと、ホントに暗くなっちゃうわ」
「ん……で、でも」
スカートにはもう誰が見ても分かるくらいクッキリと乾いたシミが付いていて、白のソックスには黄色いシミがマダラ模様になっていた。まさか歩いて帰るわけにいかないし、この時間なら間違いなく電車は満員で……
「大丈夫だって、だれも緋奈のスカートなんて見ないから」
「……」
なおも疑いの目を向けたあたしの鼻を指でつついて、玲子さんはアハハと笑った。
「行こうか」
あたしはうなずいた。
校舎にも校庭にも人の姿は見えなかった。
歩きながら怜子さんは、ユウレイとの話し方を教えてくれた。
「ほかの人には私の姿は見えないわ。だから私と話してるのを外から見たら、緋奈がひとり言を言ってると思うでしょうね」
「ふーん」
あたしは半信半疑で言った。だって怜子さんは透き通ってるわけじゃないし、足もちゃんとあって地面にはクッキリと影がついている。ユウレイだ、信じろって言われてもすぐには無理だ。
『だから私と話すときはこうするの』
「え?」
怜子さんの声が体の中から聞こえた。
『緋奈もやってみて、心の中で思うだけで通じるから』
「え……と」
『こうやって?』
『そうよ』
便利、と思うのと同時に、怜子さんがユウレイだってことをあらためて思い知らされた気がした。ちゃんと生きていたらいい友達になれたかもしれないな、と心のどこかで少し思う。
――学校の校門前で、あたしは足を止めた。
『大丈夫、誰も気づかないから』
玲子さんが言った。
『でも』
あたしはうつむいた。カァッと顔が熱くなるのがわかる。
通りには当然ながら人があふれていた。帰宅を急ぐサラリーマンから同い年くらいの学生が次々に通り過ぎていって、あたしはあわててスカートの前を鞄でかくした。
『ほら、私につっかかってきたさっきまでの緋奈はどこに行ったの?』
『そんなこと言われても……』
『ホラ』
トン、と背を押された。
「あ、だめっだ――たらっ」
トトトッとよろけながらあたしは通りに出た。知らないオジサンの背中につっこみそうになって、ビクッと立ち止まる。オジサンがくるっと振り向いた。
『どうしよう……』
とっさに鞄でスカートの前を隠した。恐る恐る見上げると、オジサンの鼻がヒクヒク動いてるのが見えた。顔をしかめながら、ふと下を向いて、目が合った!
「こんばんは」
オジサンは少し笑った。
「こ、こんにちは」
心臓が止まりそうだった。軽くオジギして、あたしはオジサンの脇を通り過ぎた。
『ばれてる』
あたしは言った。
『ぜったいにばれてる』
さっきから誰かのそばを通り過ぎるたびに鼻を押さえてこっちを見てるような気がした。何人かがあたしの方を指差して……るような気がした。
『錯覚だって』
怜子さんが言った。
『ばれてる』
あたしは言った。
『あんなに近づいても、緋奈のニオイってばれなかったじゃない』
『嘘。そんなの信じられない』
『堂々としてれば大丈夫だって、ビクビクしてると返って変に想われるよ』
『堂々って、そんなの冗談じゃないわ。ぜったい無理。それから服はどうなんの? 汚れてるのがばれたら終わりじゃない』
『だからそれは誰も見ないって』
『……もう』
と、あたしはため息をついた。でも、他の人がこっちを見るっていうのが錯覚ってことは何となく分かってきている。怜子さんの魔法はやっぱり本物で、悲惨な目にはあわないってことは何となく分かっていた。ただそれとは別に、さっきまでの旧校舎でのあたしが死ぬほど恥ずかしいのと、怜子さんにかけられた魔法が解けて普段の勝気なあたしが戻ってきたことがうれしくて、あたしは必要以上に怜子さんに突っかかっていった。
『絶対にばれてる』
『だからそれは違うって……』
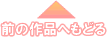

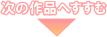
|