VS. EVE編 4
|
「はいはい。2次会でドライブ行く奴はこっち。ここでお終いの奴はお疲れさんでした」 すっかり幹事の生馬はまだみんなを仕切ってる。生馬も大人になったなぁ。だって工高の頃なら「めんどくさいから俺はやりたくない。だからお前やって〜。頼む」とか言って、ぜってー人に押し付けてる。変わり身の早いあいつはへりくだることも上手い。大抵押しつけは成功していたのだ。 2次会と称したドライブは、車で1時間ほどのH山スカイラインを走ることだった。山頂の展望台から見る夜景が綺麗なことで有名だ。酔っぱらいばっかりで何でドライブなんだか分からんのだが、ほぼ全員が車の所有者だ。走りたいんだろうな。 車5台に11人が分乗する。片側2車線以上あるところではバトルの真似事などしながら、山頂を目指す。スカイラインに入ってからは30分ほどで展望台の駐車場に着いた。 眼下に広がる夜景はそれは見事なもので、一応みんなで感動する。しかし男なんてモノは3秒で飽きる。 そのあとは柵に乗ったり、それを落とそうとしたり、変なポーズを決めて写真を取ったり、ふざけて走り回ったりして遊ぶ。 俺も心の底から笑ったのは本当に久しぶりだった。 一息ついて生馬を捜した。柵に腰を乗せ、夜景側を向いて長い足を組んでいる。ったく、黙ってればいい男なのにな。 マジで女がほっとかないだろう容姿を惜しげもなく崩す、バカをやる、ケンカをする、幼さをさらけ出す。 何でこんなに俺の心をかき乱すのか。どうしてこんなに俺は生馬を手に入れたいと思うのか。全然わからねぇ。 俺は自販機で買った熱いコーヒーの缶を持って、後ろから生馬の頬に付けてやった。 「あちっ」 生馬はびっくりしてこちらを振り向き、体勢が崩れ、かなり下方にある林に落っこちそうになる。 「アブねぇっ」 俺が伸ばした手を掴んだ。生馬の代わりにコーヒーの缶が落ちる。ザッザッと枝に受け止められているような音がしばらく聞こえ、そして消えた。 「おまっ、ずいぶん深いぞ」 しっかりと俺の腕に掴まりながら文句を言う。 「んなこと言うならおってけ」 わざと腕を前に突き出してやる。 生馬はワーワー喚くと慌ててこちら側に来た。 「せっかくコーヒー買ってきてやったのに」 「お前、わざとだろう。俺が落ちてもいいって本気で思ってなかったか?」 「コーヒー渡しただけだろう」 「いや、ぜってーわざとだ。殺気を感じたぞ」 生馬はかなり怒ってる。でもこういう怒りはいい。いつものことだし。真面目に話したことに真面目に怒りを向けられると耐えられねぇ。 まだなんか言いたそうなこいつに頭を下げた。 「俺が悪かった」 生馬に頭を下げるなんて生まれて初めてかもしれない。 「なっなんだよ。一体」 当然のように生馬は訝しむ。 「せっかくのクリスマスイブだ。サンタさんがプレゼントくれるんだぜ」 残った缶を投げる。 「こんなときにケンカなんてしたくねぇからな。謝るから仲直りしようぜ」 俺の誠心誠意を込めたつもりだった。俺が説得の顔をすると納得の顔をした。 が、しかしそれは一瞬だった。つられて少し笑ったと思ったのに。 「ばっバカ野郎。なんでお前から謝っちゃうんだよ。お前は何も悪くないのに、どうして頭下げれるんだよ。やっぱ俺のことバカにしてるんだろう!」 何だぁ。人がせっかく頭下げてんのに、何を怒る必要があるんだ。俺の堪忍袋はすぐ切れる。しかし、ここで怒ってしまっては元も子もない。グッと手を握りしめて我慢する。俺にはこいつの機嫌を取る方法が分からねぇ。 「バカになんかしてないだろう」 「してる!」 「してねぇっ」 「ぜってーしてる!」 「ぜってぇしてねぇっ」 ダメだ。もう限界だ。こんな分からず屋はぶちのめすしかねぇ。 「これだけ言っても分からねぇようだな」 「ああ、全然分からんね」 「腕ずくで分からせてやる」 「やれるもんならやってみろ」 体が自然と空手の型に入る。燃え上がった頭では何故謝ったのにこんなことになったか、なんて考えることは出来なかった。 しかしその時同じ台詞をクラスの奴らが言ってるのが聞こえてきたのだった。 えっ、誰かほかにケンカしてるのか。瞬時に頭が冷める。生馬がその隙を見逃すはずがなく、上段に突きが入った。 俺はそれを両手でしっかり受け止めて、掴んだ。 「なんだよ。それは」 びっくりして手を振って離そうとする。空手じゃあり得ないからな。 「まあ、待て。落ち着けって」 俺のその台詞に余計と頭にきたようで、もう一方の手も飛んできた。俺は腕を掴んだまま引く。両手が前に移動して、生馬の全体重が前のめりになり、俺に抱きつく格好になった。 「おい、見ろよ。女もおらんで寂しい奴らだと思ったらホモだったわ」 そのあと嘲笑が聞こえた。 そうさっきから[RED]とかいう族っぽい奴らとクラスの奴らが揉めていたのであった。 俺たちより後から来たのは知っていたが、クラスの奴らもあんなヤンキーに手を出すほどバカじゃねぇと思って気にしてなかったんだよな。 だが女の取り合いになっちまったようだ。こうなると男は歯止めがきかねぇ。ただ夜景を見に来ただけであろう女の子4人連れはいい迷惑だな。 「ホモなら女はいらんだろう」 瞬間で沸騰した俺は揉めてた奴らも押しのけて、前線に立っていた。 「誰がホモだって?」 あまり背の高くないヤンキー達は俺のガタイと剣幕にビビる。一歩出ると、一歩後ずさる。ジリッ、ジリッと追いつめる。 「抱き合ってたんだ。ホモだと思われても仕方ねぇだろうが」 手下をかき分けるようにして、どう見てもリーダー格の男が現れた。そいつの登場で今度は向こうが押してくる。人数はちょうど同じくらいだ。赤だか青だか知らねぇが俺たちゃ天下の火龍工業だぜ、 負けるわけにはいかねぇな。 「ホモだとどっちかがオカマなわけか? お前か。それともあっちか?」 カッチーン、ときた俺は答える前に正拳を突き出していた。しかしあっさりとそれは防御された。これは‥ボクシングだな。両腕を顔の前に揃えている。 考えている間に向こうも右の拳を飛ばしてきた。俺はそれを上げ受けで流す。 互いに実力が分かる。簡単に手を出せないで居ると、揉めてた原因の女の子が連れて行かれそうになる。 とうとうほかの奴らも手が出てしまった。20人あまりの大乱闘になる。だが向こうの雑魚は生馬が確実にのしていった。それに道を踏み外してないだけで、俺たちはこのへんで一番悪いって言われてる高校の卒業生だ。ケンカっ早いのが揃ってるんだ。 だんだんと向こうの分が悪くなってきた。下っ端の奴が痛みを堪えてるのか、屈んだ姿勢で鉄パイプを持ってくる。数発ずつヒットしていたトップ争いの俺たちも、そろそろ決着を付けないとアブねぇ。 生馬が下から蹴り上げるとパイプは高く回って落ちた。こっちの奴がそれを持つ。 「どうだ。もういい加減に止めないか。そっちの勝ちはねぇぞ」 「ちっ、偉そうに。これを見ても同じ台詞が言えるかよ」 追いつめられたそいつはサバイバルナイフを取り出した。 クラスの連中が引く。 「ふっふっ。これでも向かってくる勇気があるか。えっ、このおかま野郎っ」 そう言ってこちらから見て左から大振りに切り掛かる。俺はおかま野郎、のところで右上段回し蹴りを放っていた。このままいけば相打ちか。 俺の蹴りがそいつの首にヒットしたのと、しゃがんだ体勢で、左から払うように足を出した生馬の蹴りが当たったのは同時だった。 ナイフは俺の所まで届かずに、上下で違う方向に蹴られた奴は一瞬真横になって宙に浮いた。 そしてスローモーションみたいにどっと倒れる。ナイフが手から離れた。サッとこっちの奴が拾う。 リーダーが倒されたのだ。向こうに、もう覇気はない。 「どうするんだ。まだやるんかっ」 俺が怒鳴るとすごすごと引いていく。 「おい、きっちり追い込みかけとかねぇと、仕返しにきても鬱陶しいぞ」 生馬が言う。 「おい、待てよ。いいこと聞かせてやろうか。俺たちはな、火龍工業OB。チーム名はREDか。後輩全員に連絡とってもいいんだぜ」 サッと向こうの顔色が変わる。 「嘘言うんじゃねぇ」 「何なら今から電話掛けてやろうか。一体何百人集まるだろうな。みんな暴れたりねぇって言ってる奴らばっかりだからな」 「そっそんならもっと最初に言えばいいだろう」 「女は返すんで、水に流して。なっ」 180度態度を変えると慌てふためいて逃げていった。 みんなで勝ち鬨を上げる。 「お前ら、だてにケンカしてねぇな。コンビネーション、ばっちりだぜ」 「あっ、ああ。生馬、良く分かったな。あのとき俺が右の回し蹴りを入れるって」 「バカヤロ、何年付き合ってると思ってるんだ。そんなことはお見通しだぜ」 「火龍工業万歳!」 かなりボロボロになってはいたが、勝利には違いねぇ。みんな意気揚々と引き上げる。当然、命がけでゲットした女の子も一緒にだ。おかげで俺が乗せてきてもらった車から追い出された。 「俺の車に乗れよ」 珍しい。生馬からそう言ってきた。 「ちっ、仕方ねぇな。乗ってやるか」 「ったく、何でそういう言い方しかできないんだ」 車に乗り込んで暫く黙ったままで走る。 「あのよ」 「あのな」 同時に沈黙を破る声が出る。 「お前からでいいよ」 「おめぇから言えよ」 「お前が先に言えよ」 「おめぇからでいいって言ってんだろう」 「なんだと」 「このっ」 一瞬沈黙する。 そして爆笑。 「いい加減にこのパターンは止めだな」 「おう、そうだな」 「俺はさ、お前とライバルで居たかったんだよ。なのにお前だけがどんどん大人になっていって。悔しかったんだ」 「ライバルだろう」 「いや、俺だけ甘やかされてた。俺のために煙草我慢したり、同じ工高に来たり、全然気が付かなかった。それなのに自分から謝ってくるし。大人の余裕を見せつけられてメチャクチャに悔しかった」 大人の余裕だなんて‥。そんなモノが全然無いから必死になってこいつの嫌いなことはしないようにしようと思ってただけなのに。そばから離れられなかっただけなのに。 「俺は余裕がなさ過ぎていつも焦ってたんだ。どうやったらおめぇを手に入れれるか、そればっかり考えてた。離れていって欲しくなかった」 生馬はハンドルを握りながらニヤッとする。 「なぁ、今日ってクリスマスイブだよな」 「ああ」 「サンタさんがプレゼントくれるんだよな」 「ああ、そうだ」 「俺がサンタになってやるよ」 ん? 俺が訳が分からないって顔をすると、生馬はこう言った。 「週末は毎週そっちに行ってやるから」 ええっ、なんて言った。 「俺って言うプレゼントを受け取りたかったら、そっちは合い鍵をプレゼントするんだな」 俺は嬉しくて飛び上がりそうになりながら、普段のポーズが捨てきれねぇ。 「ちっ、しょうがねぇな。真っ先に合い鍵を作っておめぇにやるよ。ほかの奴にはぜってぇ渡さねぇ」 「ふふっ、俺だけってか。そりゃいい」 「そうだ、だから必ず来るんだぜ。部屋では一切煙草も吸わねぇ」 「ああ、行くよ。行ってやるよ」 とても、とても穏やかな気持ちだ。こんな気持ちはこいつと会ってから味わったことがないかもしれない。 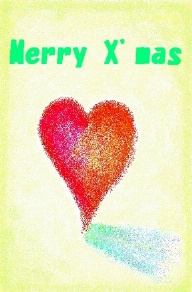 「今日は俺んちに来いよ。どうしても抱きたい」
「今日は俺んちに来いよ。どうしても抱きたい」「今日こそは俺が抱くんだからな」 「何だよ。クリスマスだぜ。プレゼントしてくれるんじゃねぇのかよ」 「そっちからのプレゼントが今はないだろう。だから今日は俺がやる」 「何だよそれは。やっぱり決着つけなきゃならんようだな」 「おおっ、いつでも受けて立つぜ」 「今日こそやってやる」 「こっちの台詞だ」 どうしてもこの関係は変わりそうもない。 でもなぜかとても幸せだった。 そうだ、サンタさんにお礼を言わなきゃな。ありがとうって。 そしてメリークリスマス! 終わり
|
前へ ・分校目次 ・愛情教室 ・あとがき